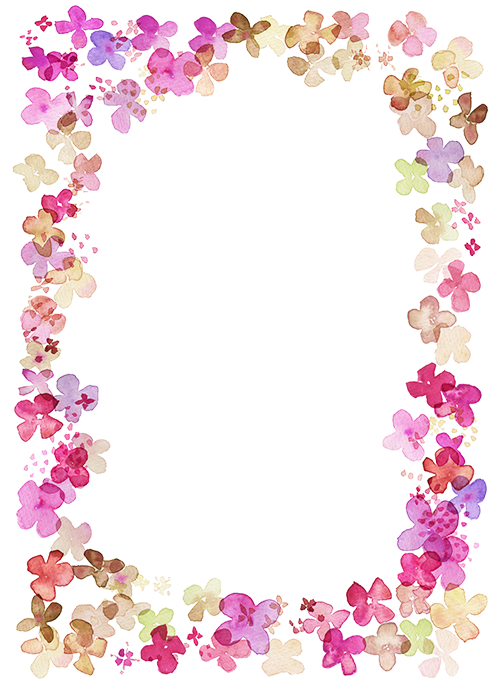あまりにもひどい言葉を投げかけられて一瞬絶句したが、ここでひるんではいけない。
「寝てろよ。俺、適当に何か食うから」
「違うよ」
「具合が悪いのか? ゆっくりしろよ」
「気持ち悪い」
急に優しくなった彼の顔に、私はそう吐き捨てた。
オレンジ色の間接照明ひとつつけただけのダイニングが少し暗くなったように思えた。エアコンは彼がキンキンにした。冷凍庫の中にいるようだった。
「私もフルタイムで働いてるの知ってるよね」
「でもそれっていつでも辞められる仕事だよな」
「医療秘書は立派な仕事だよ。資格も要る。私、契約から正社員になったの」
「でもそれっておまえじゃなくてもできる仕事だよな? ただ、病院の受付に座ってニコニコしてりゃ良いんだし」
「私の夫はおまえじゃなくても良い」
しめ忘れたカーテン。大窓から住宅街のぬくもりあふれる灯りが見える。おいしい夕食のにおいがしそうなほど、暖色。
「『おまえ』!? おまえ、俺に向かって何様だよ!!」
「おまえこそ何様だよ。
彼氏だった頃はあんなに優しかったの、ただ、セ**スの相手が欲しいだけだったんだね。動物じゃん」
響きわたる彼の悲鳴のような怒声と、どんどん低くなっていく私の声。温度差。エアコンの温度の好みが違うだけじゃない。愛の温度の好みも違うと気付いてしまった。
「俺が毎日家庭のために汗水垂らして働いてるって言うのに!!」
「私は仕事に加えて家事もご近所付き合いも家の事務も経理もしてる。汗水垂らしてね」
「それが妻の仕事だろ!!」
「妻、やめるわ」
「寝てろよ。俺、適当に何か食うから」
「違うよ」
「具合が悪いのか? ゆっくりしろよ」
「気持ち悪い」
急に優しくなった彼の顔に、私はそう吐き捨てた。
オレンジ色の間接照明ひとつつけただけのダイニングが少し暗くなったように思えた。エアコンは彼がキンキンにした。冷凍庫の中にいるようだった。
「私もフルタイムで働いてるの知ってるよね」
「でもそれっていつでも辞められる仕事だよな」
「医療秘書は立派な仕事だよ。資格も要る。私、契約から正社員になったの」
「でもそれっておまえじゃなくてもできる仕事だよな? ただ、病院の受付に座ってニコニコしてりゃ良いんだし」
「私の夫はおまえじゃなくても良い」
しめ忘れたカーテン。大窓から住宅街のぬくもりあふれる灯りが見える。おいしい夕食のにおいがしそうなほど、暖色。
「『おまえ』!? おまえ、俺に向かって何様だよ!!」
「おまえこそ何様だよ。
彼氏だった頃はあんなに優しかったの、ただ、セ**スの相手が欲しいだけだったんだね。動物じゃん」
響きわたる彼の悲鳴のような怒声と、どんどん低くなっていく私の声。温度差。エアコンの温度の好みが違うだけじゃない。愛の温度の好みも違うと気付いてしまった。
「俺が毎日家庭のために汗水垂らして働いてるって言うのに!!」
「私は仕事に加えて家事もご近所付き合いも家の事務も経理もしてる。汗水垂らしてね」
「それが妻の仕事だろ!!」
「妻、やめるわ」