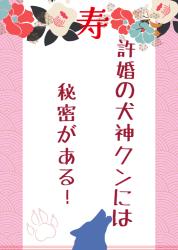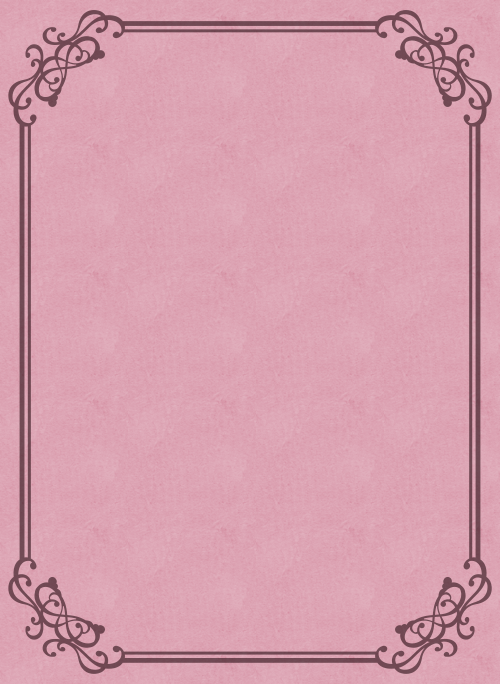電話が切れると、一抹の名残惜しさを抱かせて一ノ瀬さんの手が離れていった。
「私は好感度上げたりとか、お世辞言ったりするのが苦手・・・」
「はぁ~だろうね。知ってるよ」
昔から『変わってる』と言われる。自分では普通のつもりだけど他人から見ると普通ではないらしい。『どこが?』と聞いても明確な答えは返ってこない。それが良いのか悪いのかもわからなかった。
――でも、あの日『それが如月さんのいいところなんじゃないの?』そう一ノ瀬さんに声をかけられて変わったきっと本人は忘れてるだろうけど。
だから、一ノ瀬さんにはちゃんと伝えようと心掛けてる。
「それでも一ノ瀬さんが誘ってくれたのは嬉しかったです。できたらまた誘って欲しとも思います」
一ノ瀬さんを見ると、目を丸くさせながら瞬きを繰り返している。少ししてから、はぁとため息をついた。
「っ・・・もぉ何それ。ずるいよ、如月さん」
「何がですか?」
「そういう・・・嬉しいことサラッと無自覚で言うから」
ずるいのは一ノ瀬さんの方、と言おうとしたら胸の奥が締め付けられて言えなくなった。急に苦しくなって、唇の内側を噛み気持ちを抑え込もうとした。
「また誘うよ。だから何が食べたいか教えて。今度は如月さんが美味しいって喜んでくれる顔が見たいから」
「なんか今数多の女を誘い慣れているチャラい男感がぷんぷんとした」
「さっきも言ったけど俺はチャラくないから。彼女もいないし・・・好きな子はいるけど」
「好きな人?」
「そう。もうずっと前から片想い中」
「そうですか・・・。上手くいくといいですね」
笑っていた一ノ瀬さんが、一度だけ真剣に私を見つめた。それ以上見つめられると、本当に暴かれてしまいそうになるので、そっと目を逸らした。
ずっと前から片想い中なんて、私の入る隙は微塵もなさそうだ。
□□□
「うわぁ~ん!如月先ぱぁーい!!本当にすみませんでした」
「大丈夫。それより始末書早く書こう」
「僕もう自信喪失です・・・」
「これ始末書ね、まずは書ける範囲書いて」
「うぅぅやっぱり先輩怒ってますか!?ごめんなさい!!あっ僕今日お昼奢ります!」
「始末書書いて」
デスクに戻って来るなり湊君に泣きつかれた。素直で良い子だけれど仕事ができない。新入社員でありながら既に三度の部署替えを経験済み。
ようやく腰を下ろすと、ふぅと息が漏れた。なんだかどっと疲れた・・・。
「お疲れ。大変だったね~」
「本当に。大変だった」
隣の席で同僚の栗林夢乃(クレバヤシユメノ)が労いの声を掛けてくれた。夢乃とは大学から一緒で、気の知れた仲だった。
「お昼まだなら先に行ってきたら?」
「さっき一ノ瀬さんと行ってきた」
「一ノ瀬君?・・・まだやり取りあるんだ。企画部行ってから全然話さなくなったな~」
「そうなの?私、よく会うけど」
「ふ~ん。そういえば一ノ瀬君って入社の時から莉子のこと気にかけてたよね」
「気にかけるって?」
「ん~いつだったかな。莉子がクライアントに叱られた仕事を一ノ瀬さんが引き継いだりとかなかった?」
「あった・・・」
「案外一ノ瀬君、莉子のことが好きとか?」
夢乃の言葉にキーボードを打っている手が止まった。
「まさか。好きな人はいるみたいだけど・・・。だいたい黒川部長に知られたら面倒だし、わざわざ会社に恋愛を持ち込まないよ」
「へぇ一ノ瀬君好きな人いるんだ。なんか意外ね。でもさぁ~頭ではわかってても心が動いちゃうのが恋じゃない?」
「私はよくわからない」
「んもぉー!莉子は相変わらず恋愛に対して鈍いんだから」
「そんなことない。私だって一ノ瀬さんにドキドキはする」
「え!?何よドキドキしてるんじゃない!」
違う、と言いかけて喉元で言葉がつまった。夢乃がニヤニヤ顔で私を見てくる。
「・・・ちょっと確かめてくる」
「確かめるって何を?」
「本当にドキドキしたか一ノ瀬さんに確かめないと。なんか悔しい」
「はぁ?やめときなさいよ。今仕事中でしょ」
立ち上がると夢乃に慌てて止められた。モヤモヤする。これじゃ一ノ瀬さんに振り回されてるみたいだ。とりあえず、今日帰る時間を教えて欲しいと連絡をいれておいた。会いたいとかではない。断じてない!
「如月さ~ん。社内コンペの『恋人と食べたい夏のスイーツ』の計画書まだ出てないわよ」
「あっすみません。まだ書けてなくて・・・あっそうだ!今良いアイディアが降りてきましたよ!『水まんじゅうで包もう愛の巣』とかどうですか?」
「今月までだからよろしくね~」
「・・・はっはい」
無言で却下されてしまった。
我社ではシーズンごとに商品の提案を社員から募る。食と季節を交えたコンペで優勝企画は来年の商品化が決定となる、まさに一大コンペだ。
「ぷっ。今時、愛の巣って。まだ社内コンペの計画書出してなかったの?いつも早いのに」
「仕事が立て込んでるのもあるけど、何よりテーマが・・・」
「ほら昔社内恋愛禁止してたでしょ?そこの需要が著しく弱いから伸ばしたいらしいわよ」
「悪しき風習の名残がここにきて・・・。ダメだ。これじゃコルネ王子に到底及ばない」
「コルネ王子?誰それ」
「私の心の支え。コルネ王子のことを考えると不思議と企画が舞い降りてくるの」
「あー、前からよく話に出て来るお得意の妄想ねぇ」
――コルネ王子とは実在する人物である。初めて参加した社内コンペ。その時、接戦で落ちてしまったのがコルネ王子だ。基盤の中にありながら隙をついた企画は今でも覚えている。以来、コルネ王子に秘かに憧れている。無記名だから顔も名前も知らない人だけど、きっと素敵な人に違いない。今回の企画、コルネ王子だったらどうするかな。
□□□
「なっなぜ、終わりが見えない」
「先に帰るよ~お疲れ」
「お疲れ様」
社員が帰宅に向かう中パソコンに向き合っていると、スマホに通知がきていた。一ノ瀬さんからだ。今から帰ると、十五分前にメッセージが届いている。
いけない!昼間のこと確認するんだった。慌てて一階下の企画部へと向かった。エレベーターに乗り込むと、ガラス張りの窓から一階の様子が見えた。仕事を終え帰路に着く社員の中に一ノ瀬さんらしき人影を見つけた。すぐに一階のボタンを連打した。
「一ノ瀬さん!」
開きかけのドアから名前を呼んだ。一ノ瀬さんが私に気付く振り返り足を止めてくれている。駆け寄ると、周りに一緒にいた人が軽く挨拶をして帰っていく。
「どうしたの?返事こないからもう帰ったのかと思った」
「一ノ瀬さんに確かめたいことがあって」
「確かめたいこと?」
「手貸してください」
「・・・手?」
一ノ瀬さんは不思議そうに顔の前で手を広げた。私はその手をすかさず握った。
「え、何?」
「一ノ瀬さんに手を握られてドキドキした気がしたので、本当だったかどうか確かめに来ました」
「・・・はぁ?」
「ドキドキは恋ですか?一ノ瀬さんもドキドキしますか?」
「するって言ったらどうするの。好きになってくれるわけ?」
「私が?一ノ瀬さんを?」
夢乃の言葉を思い出した。恋の始まりはどこからなんだろう。ドキドキはイコールで恋に繋がるのか?違うと私は否定したくなった。
「そんなこと絶対にありえません」
「・・・あのさ無自覚にも限度があるでしょ」
ほんの一瞬、一ノ瀬さんの顔に黒い影が落ちたように見えた。握っている手を突然引っ張られる。広いロビーにバタバタと自分の足音が雑に響いて行く。
「えっちょっと!」
そのまま角を曲がり奥にあるリモートブースに押し込まれた。一人用のブースは二人で入るには狭い。バンッと薄いドアが閉まると同時に身体が密着した。心臓の鼓動がドクッと響いてくる。逃げられないように、私の身体を挟み込むようにして壁に手を付いていた。全くと言っていいほど状況が読み込めない。
「そんなに確かめたいなら、教えてあげる」
一ノ瀬さんが顔を近づけて、いつもよりも低い声で囁くから身体が震えた。一ノ瀬さんの身体を引き離そうと胸板を力いっぱい押したけどビクともしない。
「はいはい、じゃ手はこっち」
「あ、あの一ノ瀬さんっ」
「顔、真っ赤。可愛い」
「んっ・・・ちょっと」
不意を突かれたように唇をふさがれた。反射的に目を閉じると、二人の吐息が混ざり合うように零れていく。密着した一ノ瀬さんの体温が薄いシャツ越しに伝わってくる。
「こ、これくらいじゃ、ドキドキしません!もうわかったので離してください」
「じゃちゃんと俺の目を見て言って」
「・・・っ」
「言っとくけど誘ってきたのは如月さんだから」
ニッと口角を上げ狡猾に笑う一ノ瀬さん。悔しいと思う私に、追い打ちをかけるように「ドキドキした?」と試すように聞いてくる。これでは昼間以上に振り回されてる。
気がつけば離れてく一ノ瀬さんのネクタイを、自分の方へ思いきり引っ張り唇を重ねていた。何をしているのか自分でも理解できなかったけど、一ノ瀬さんがとても驚いていたのでしてやったりと言ったところか。
「ドキドキした?い、一ノ瀬さんは他の人もするから足りない?」
「言ってることもやってることも、めちゃくちゃだよ如月さん。俺は好きな子にしか、こういうことしない」
そう言ってまた唇を重ねてくる一ノ瀬さんは嘘つきだ――
□□□
周りの高いビルの間をすり抜け、太陽の光がオフィス窓のから太フロア全体を照らしている。朝礼を終え、パソコンに向かうも仕事が手に着かない。
「どうしたの莉子?顔色悪いわよ」
「えっいや、全然元気!仕事頑張るぞー!」
「明らかにテンションおかしいでしょう。残業しすぎで疲れてんじゃないの?」
残業ではなく一ノ瀬さんのせい。とはさすがに言えない。 結局、あの後、いたたまれなくなりそのまま逃げだしてしまった。呼び止められてる気がしたけど向ける顔がない。一ノ瀬さんは一番好きになっちゃいけないタイプだ。恋愛に鈍い私でもそれくらいはわかる。
「今日は気分転換に飲みにでも行く?」
「うん・・・私も聞いて欲しい話がある」
パソコンの画面に薄っすらと自分の顔が映り込む。唇に昨日の感触が今でも鮮明に蘇ってくる。零れる吐息や息遣い、角ばった指先、お互いに早くなっていく鼓動。一ノ瀬さんはどうしてキスしたんだろう。
「私は好感度上げたりとか、お世辞言ったりするのが苦手・・・」
「はぁ~だろうね。知ってるよ」
昔から『変わってる』と言われる。自分では普通のつもりだけど他人から見ると普通ではないらしい。『どこが?』と聞いても明確な答えは返ってこない。それが良いのか悪いのかもわからなかった。
――でも、あの日『それが如月さんのいいところなんじゃないの?』そう一ノ瀬さんに声をかけられて変わったきっと本人は忘れてるだろうけど。
だから、一ノ瀬さんにはちゃんと伝えようと心掛けてる。
「それでも一ノ瀬さんが誘ってくれたのは嬉しかったです。できたらまた誘って欲しとも思います」
一ノ瀬さんを見ると、目を丸くさせながら瞬きを繰り返している。少ししてから、はぁとため息をついた。
「っ・・・もぉ何それ。ずるいよ、如月さん」
「何がですか?」
「そういう・・・嬉しいことサラッと無自覚で言うから」
ずるいのは一ノ瀬さんの方、と言おうとしたら胸の奥が締め付けられて言えなくなった。急に苦しくなって、唇の内側を噛み気持ちを抑え込もうとした。
「また誘うよ。だから何が食べたいか教えて。今度は如月さんが美味しいって喜んでくれる顔が見たいから」
「なんか今数多の女を誘い慣れているチャラい男感がぷんぷんとした」
「さっきも言ったけど俺はチャラくないから。彼女もいないし・・・好きな子はいるけど」
「好きな人?」
「そう。もうずっと前から片想い中」
「そうですか・・・。上手くいくといいですね」
笑っていた一ノ瀬さんが、一度だけ真剣に私を見つめた。それ以上見つめられると、本当に暴かれてしまいそうになるので、そっと目を逸らした。
ずっと前から片想い中なんて、私の入る隙は微塵もなさそうだ。
□□□
「うわぁ~ん!如月先ぱぁーい!!本当にすみませんでした」
「大丈夫。それより始末書早く書こう」
「僕もう自信喪失です・・・」
「これ始末書ね、まずは書ける範囲書いて」
「うぅぅやっぱり先輩怒ってますか!?ごめんなさい!!あっ僕今日お昼奢ります!」
「始末書書いて」
デスクに戻って来るなり湊君に泣きつかれた。素直で良い子だけれど仕事ができない。新入社員でありながら既に三度の部署替えを経験済み。
ようやく腰を下ろすと、ふぅと息が漏れた。なんだかどっと疲れた・・・。
「お疲れ。大変だったね~」
「本当に。大変だった」
隣の席で同僚の栗林夢乃(クレバヤシユメノ)が労いの声を掛けてくれた。夢乃とは大学から一緒で、気の知れた仲だった。
「お昼まだなら先に行ってきたら?」
「さっき一ノ瀬さんと行ってきた」
「一ノ瀬君?・・・まだやり取りあるんだ。企画部行ってから全然話さなくなったな~」
「そうなの?私、よく会うけど」
「ふ~ん。そういえば一ノ瀬君って入社の時から莉子のこと気にかけてたよね」
「気にかけるって?」
「ん~いつだったかな。莉子がクライアントに叱られた仕事を一ノ瀬さんが引き継いだりとかなかった?」
「あった・・・」
「案外一ノ瀬君、莉子のことが好きとか?」
夢乃の言葉にキーボードを打っている手が止まった。
「まさか。好きな人はいるみたいだけど・・・。だいたい黒川部長に知られたら面倒だし、わざわざ会社に恋愛を持ち込まないよ」
「へぇ一ノ瀬君好きな人いるんだ。なんか意外ね。でもさぁ~頭ではわかってても心が動いちゃうのが恋じゃない?」
「私はよくわからない」
「んもぉー!莉子は相変わらず恋愛に対して鈍いんだから」
「そんなことない。私だって一ノ瀬さんにドキドキはする」
「え!?何よドキドキしてるんじゃない!」
違う、と言いかけて喉元で言葉がつまった。夢乃がニヤニヤ顔で私を見てくる。
「・・・ちょっと確かめてくる」
「確かめるって何を?」
「本当にドキドキしたか一ノ瀬さんに確かめないと。なんか悔しい」
「はぁ?やめときなさいよ。今仕事中でしょ」
立ち上がると夢乃に慌てて止められた。モヤモヤする。これじゃ一ノ瀬さんに振り回されてるみたいだ。とりあえず、今日帰る時間を教えて欲しいと連絡をいれておいた。会いたいとかではない。断じてない!
「如月さ~ん。社内コンペの『恋人と食べたい夏のスイーツ』の計画書まだ出てないわよ」
「あっすみません。まだ書けてなくて・・・あっそうだ!今良いアイディアが降りてきましたよ!『水まんじゅうで包もう愛の巣』とかどうですか?」
「今月までだからよろしくね~」
「・・・はっはい」
無言で却下されてしまった。
我社ではシーズンごとに商品の提案を社員から募る。食と季節を交えたコンペで優勝企画は来年の商品化が決定となる、まさに一大コンペだ。
「ぷっ。今時、愛の巣って。まだ社内コンペの計画書出してなかったの?いつも早いのに」
「仕事が立て込んでるのもあるけど、何よりテーマが・・・」
「ほら昔社内恋愛禁止してたでしょ?そこの需要が著しく弱いから伸ばしたいらしいわよ」
「悪しき風習の名残がここにきて・・・。ダメだ。これじゃコルネ王子に到底及ばない」
「コルネ王子?誰それ」
「私の心の支え。コルネ王子のことを考えると不思議と企画が舞い降りてくるの」
「あー、前からよく話に出て来るお得意の妄想ねぇ」
――コルネ王子とは実在する人物である。初めて参加した社内コンペ。その時、接戦で落ちてしまったのがコルネ王子だ。基盤の中にありながら隙をついた企画は今でも覚えている。以来、コルネ王子に秘かに憧れている。無記名だから顔も名前も知らない人だけど、きっと素敵な人に違いない。今回の企画、コルネ王子だったらどうするかな。
□□□
「なっなぜ、終わりが見えない」
「先に帰るよ~お疲れ」
「お疲れ様」
社員が帰宅に向かう中パソコンに向き合っていると、スマホに通知がきていた。一ノ瀬さんからだ。今から帰ると、十五分前にメッセージが届いている。
いけない!昼間のこと確認するんだった。慌てて一階下の企画部へと向かった。エレベーターに乗り込むと、ガラス張りの窓から一階の様子が見えた。仕事を終え帰路に着く社員の中に一ノ瀬さんらしき人影を見つけた。すぐに一階のボタンを連打した。
「一ノ瀬さん!」
開きかけのドアから名前を呼んだ。一ノ瀬さんが私に気付く振り返り足を止めてくれている。駆け寄ると、周りに一緒にいた人が軽く挨拶をして帰っていく。
「どうしたの?返事こないからもう帰ったのかと思った」
「一ノ瀬さんに確かめたいことがあって」
「確かめたいこと?」
「手貸してください」
「・・・手?」
一ノ瀬さんは不思議そうに顔の前で手を広げた。私はその手をすかさず握った。
「え、何?」
「一ノ瀬さんに手を握られてドキドキした気がしたので、本当だったかどうか確かめに来ました」
「・・・はぁ?」
「ドキドキは恋ですか?一ノ瀬さんもドキドキしますか?」
「するって言ったらどうするの。好きになってくれるわけ?」
「私が?一ノ瀬さんを?」
夢乃の言葉を思い出した。恋の始まりはどこからなんだろう。ドキドキはイコールで恋に繋がるのか?違うと私は否定したくなった。
「そんなこと絶対にありえません」
「・・・あのさ無自覚にも限度があるでしょ」
ほんの一瞬、一ノ瀬さんの顔に黒い影が落ちたように見えた。握っている手を突然引っ張られる。広いロビーにバタバタと自分の足音が雑に響いて行く。
「えっちょっと!」
そのまま角を曲がり奥にあるリモートブースに押し込まれた。一人用のブースは二人で入るには狭い。バンッと薄いドアが閉まると同時に身体が密着した。心臓の鼓動がドクッと響いてくる。逃げられないように、私の身体を挟み込むようにして壁に手を付いていた。全くと言っていいほど状況が読み込めない。
「そんなに確かめたいなら、教えてあげる」
一ノ瀬さんが顔を近づけて、いつもよりも低い声で囁くから身体が震えた。一ノ瀬さんの身体を引き離そうと胸板を力いっぱい押したけどビクともしない。
「はいはい、じゃ手はこっち」
「あ、あの一ノ瀬さんっ」
「顔、真っ赤。可愛い」
「んっ・・・ちょっと」
不意を突かれたように唇をふさがれた。反射的に目を閉じると、二人の吐息が混ざり合うように零れていく。密着した一ノ瀬さんの体温が薄いシャツ越しに伝わってくる。
「こ、これくらいじゃ、ドキドキしません!もうわかったので離してください」
「じゃちゃんと俺の目を見て言って」
「・・・っ」
「言っとくけど誘ってきたのは如月さんだから」
ニッと口角を上げ狡猾に笑う一ノ瀬さん。悔しいと思う私に、追い打ちをかけるように「ドキドキした?」と試すように聞いてくる。これでは昼間以上に振り回されてる。
気がつけば離れてく一ノ瀬さんのネクタイを、自分の方へ思いきり引っ張り唇を重ねていた。何をしているのか自分でも理解できなかったけど、一ノ瀬さんがとても驚いていたのでしてやったりと言ったところか。
「ドキドキした?い、一ノ瀬さんは他の人もするから足りない?」
「言ってることもやってることも、めちゃくちゃだよ如月さん。俺は好きな子にしか、こういうことしない」
そう言ってまた唇を重ねてくる一ノ瀬さんは嘘つきだ――
□□□
周りの高いビルの間をすり抜け、太陽の光がオフィス窓のから太フロア全体を照らしている。朝礼を終え、パソコンに向かうも仕事が手に着かない。
「どうしたの莉子?顔色悪いわよ」
「えっいや、全然元気!仕事頑張るぞー!」
「明らかにテンションおかしいでしょう。残業しすぎで疲れてんじゃないの?」
残業ではなく一ノ瀬さんのせい。とはさすがに言えない。 結局、あの後、いたたまれなくなりそのまま逃げだしてしまった。呼び止められてる気がしたけど向ける顔がない。一ノ瀬さんは一番好きになっちゃいけないタイプだ。恋愛に鈍い私でもそれくらいはわかる。
「今日は気分転換に飲みにでも行く?」
「うん・・・私も聞いて欲しい話がある」
パソコンの画面に薄っすらと自分の顔が映り込む。唇に昨日の感触が今でも鮮明に蘇ってくる。零れる吐息や息遣い、角ばった指先、お互いに早くなっていく鼓動。一ノ瀬さんはどうしてキスしたんだろう。