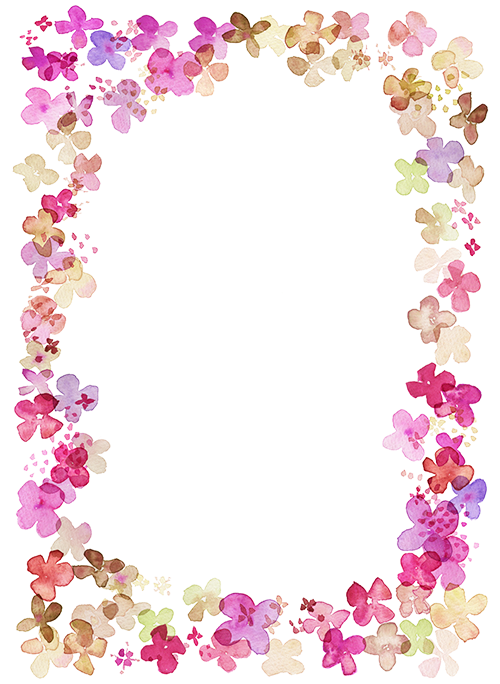名前ではなく失敗談で呼ばれて、顔から火が出るほど恥ずかしかった。恥ずかしくてその場から逃げだしたいのに、足が根を張って動けない。からだはつめたくこおってしまった。
「何見てんだよ」
きみはいたずらっぽくそう言った。悪い気がしていないニュアンスだった。
「ダンス好きなの?」
僕は答えられなかった。アイドルもよく知らないし、体育の授業ではフォークダンスしか踊ったことがない。好きか嫌いかと言えば、「よくわからない」が正解だった。
「じゃあ、好きになりなよ」
潮風の色が見えたようだった。
きみの澄んだ目の中に、
海があり、空があり、風があり、
そして僕がいた。
混乱する頭の中で何度も何度も、踊るきみが再生されていた。
おだやかな音楽のように。胸を揺さぶり、だが、安らかに眠らせる鼓動のように。
何かを言おうとして唇が震えた。凍えていた。乾いていた。
きみの澄んだ目が柔らかい孤をえがいていた。下の濃いまつ毛が地平線のようだった。
「Beautiful」
「何見てんだよ」
きみはいたずらっぽくそう言った。悪い気がしていないニュアンスだった。
「ダンス好きなの?」
僕は答えられなかった。アイドルもよく知らないし、体育の授業ではフォークダンスしか踊ったことがない。好きか嫌いかと言えば、「よくわからない」が正解だった。
「じゃあ、好きになりなよ」
潮風の色が見えたようだった。
きみの澄んだ目の中に、
海があり、空があり、風があり、
そして僕がいた。
混乱する頭の中で何度も何度も、踊るきみが再生されていた。
おだやかな音楽のように。胸を揺さぶり、だが、安らかに眠らせる鼓動のように。
何かを言おうとして唇が震えた。凍えていた。乾いていた。
きみの澄んだ目が柔らかい孤をえがいていた。下の濃いまつ毛が地平線のようだった。
「Beautiful」