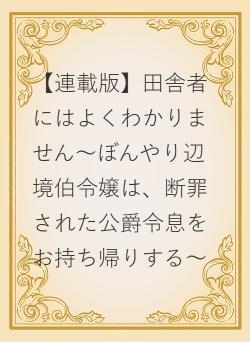この国の第一王子として生まれたローレルは、弟のシオンが生まれるまで、自分の人生に少しの疑問も持たずに生きていた。
ローレルとシオンは、両親や乳母でさえ見分けがつかないほど外見が似ているのに、まったく違う生き物だった。
ローレルはシオンを見るたびに思った。
――シオンは、どうしてこんなに簡単なことができないのだろう。
――シオンは、どうしてもっとうまく立ち回れないのだろう。
日々の疑問は、少しずつローレルの中に不快感として積み重なっていく。周りの大人たちはローレルのことを『完璧な王子様』と褒めたたえる。完璧であるがゆえに、ローレルにできないことはなかった。
シオンはというと、とにかく何でも最初はできないことばかりだった。しかし、大人たちはシオンに「それで良いのです。初めはできなくて当たり前です」と優しく語りかけている。
(シオンは愚かだな)
そう思っていたのに、何もできないシオンは、練習を繰り返し、少しずつできるようになっていった。できないことができるようになった時のシオンの幸せそうな顔を見て、ローレルは初めて『自分は何か大切な感情を味わっていないのではないか?』と疑問に思った。
完璧なので、努力なんてする必要がない。挫折や後悔なんて一生味わうこともない。ただ、それは、できないことができるようになるという達成感を味わうこともないということだった。
全てが思い通りになる日々は、ローレルの心に小さな穴を空けた。
成長と共に心の穴はどんどん大きくなり広がっていく。いつの日か、この穴は、ローレルの全てを飲み込んでしまうかもしれない。
(シオンさえいなければ、私は完璧のままだったのに)
不快感からローレルはシオンのふりをして悪いことをするようになった。もちろん誰も気がつかない。ローレルは、楽しいと同時にとてもつまらないと感じた。
こんな子どもに騙される大人たちが愚かに見えて仕方がない。楽しくて、そして、つまらない日々。
そんなある日、王宮で開かれたお茶会で、いつものようにシオンにイタズラの罪をなすりつけていると、小さな女の子に見抜かれた。
「今、その子が転んだのは、シオン殿下のせいじゃないわ。私、見ていたもの」
真っすぐにローレルを見つめる瞳に、少しだけ動揺した。しかし、すぐに冷静になり、女の子を人気《ひとけ》のないところへ連れて行き脅して解決した。
何も問題はない。ただ、少しだけ面白いなとは思った。そして、そんなつまらないことはすぐに忘れた。
女の子のことを思い出したのは、学園に『オルウェン伯爵家の娘が入学した』と聞いたときだった。
(オルウェン……。セリー商会を通じて裏社会に密接している、あのオルウェンか)
子どものころは裏社会のことまでは知らなかったが、オルウェン伯爵家はなかなか特殊な貴族だった。そのことに気がついているのは、ごくごく一部の王族と上位貴族だけだ。
(おしいことをしたな)
子どものころに出会ったあのお茶会の場で、オルウェンの娘リナリアを脅すのではなく口説いていれば利用できたのにと少しだけ後悔した。
(後悔? 私が?)
後悔している自身に驚いたが、そのときはそれだけだった。しかし、不思議なことに弟のシオンがリナリアに執着していた。
(相変わらず我が弟は愚かだな)
リナリアは、どこにでもいるような外見だし、突出して優秀なわけでもない。一度、群衆の中に紛れ込んでしまうと絶対に見つけられないような凡人だ。
(シオンは、リナリアを利用して、私と敵対でもするつもりか?)
確かにオルウェンという家柄だけは魅力的だが、王家を毛嫌いしているオルウェンと手を組むのは不可能だろう。
(シオン、もう少し私を楽しませてよ)
このままあまりにもつまらない日々が続くのなら、いっそのこと、この国ごと全部壊してしまいたくなる。
この国の初代国王は、各勢力が武力で争っている中、交渉だけで争いを終結させて一つの国へとまとめ上げた偉大な王だと言われている。
(だったら、私は、武力を使わず交渉だけで、この国の全てを壊してしまおうかな?)
ローレルは子どものころからずっと『初代王の再来』と言われているので、それくらいなら簡単にできそうだ。
(うん、そうしよう。私が学園を卒業するまでに面白いことが一つもおこらなければ、この国を壊そう)
そう決めてローレルは、学園生活を送っていた。五年間通い今年で卒業だが、未だに一つも面白いことが起こっていない。
だから、ローレルは自分から面白いことを探し始めた。今、一番面白そうなのは、リナリア=オルウェンだ。
シオンと付き合っているらしいので、シオンの振りをして近づいた。
リナリアの瞳を見てすぐに『二人の王子を見分けられている』と気がついた。なぜなら、リナリアの瞳には嫌悪が浮かんでいた。それは決して恋人に向けるものではない。
(私がローレルと分かっていて、こんな態度を取られたのは初めてだ)
ポッカリと空いた心の穴に、感じるはずのないかすかな痛みを感じた。
リナリアと手を繋ぐと、リナリアはまるで不快なものにさわられたように顔を青くしている。
(今、私がローレルと分かった上で、気持ち悪がられているんだ。リナリアは、私のことが気持ち悪いんだ)
試しにリナリアを抱きしめてみると、全力で嫌がられた。
(人って、私に媚びたり、私の機嫌をとったり、称賛したりする以外の行動もとるんだ! すごく、すごく面白いよ!)
リナリアは、二人の王子を見分けられることを必死に隠しているようで、ローレルに何をされても耐えている。
(どこまで耐えるの?)
試しにスカートの上からリナリアの太ももにふれると、リナリアは小さく息を吸った。悲鳴をあげるのを耐えているらしい。
(そんなに私のことが嫌?)
今までされたことのない反応が新鮮で面白すぎて胸がときめく。
「こんなに怯えて。リナリアは可愛いね」
この言葉は本心からだった。
(シオンがリナリアに執着する理由が、今、分かった)
自分を見分けてくれる人間がこんなにも嬉しいだなんて知らなかった。
(私もリナリアが欲しいよ。いつもみたいに、もらうねシオン)
ローレルはニッコリと微笑んだ。
ローレルとシオンは、両親や乳母でさえ見分けがつかないほど外見が似ているのに、まったく違う生き物だった。
ローレルはシオンを見るたびに思った。
――シオンは、どうしてこんなに簡単なことができないのだろう。
――シオンは、どうしてもっとうまく立ち回れないのだろう。
日々の疑問は、少しずつローレルの中に不快感として積み重なっていく。周りの大人たちはローレルのことを『完璧な王子様』と褒めたたえる。完璧であるがゆえに、ローレルにできないことはなかった。
シオンはというと、とにかく何でも最初はできないことばかりだった。しかし、大人たちはシオンに「それで良いのです。初めはできなくて当たり前です」と優しく語りかけている。
(シオンは愚かだな)
そう思っていたのに、何もできないシオンは、練習を繰り返し、少しずつできるようになっていった。できないことができるようになった時のシオンの幸せそうな顔を見て、ローレルは初めて『自分は何か大切な感情を味わっていないのではないか?』と疑問に思った。
完璧なので、努力なんてする必要がない。挫折や後悔なんて一生味わうこともない。ただ、それは、できないことができるようになるという達成感を味わうこともないということだった。
全てが思い通りになる日々は、ローレルの心に小さな穴を空けた。
成長と共に心の穴はどんどん大きくなり広がっていく。いつの日か、この穴は、ローレルの全てを飲み込んでしまうかもしれない。
(シオンさえいなければ、私は完璧のままだったのに)
不快感からローレルはシオンのふりをして悪いことをするようになった。もちろん誰も気がつかない。ローレルは、楽しいと同時にとてもつまらないと感じた。
こんな子どもに騙される大人たちが愚かに見えて仕方がない。楽しくて、そして、つまらない日々。
そんなある日、王宮で開かれたお茶会で、いつものようにシオンにイタズラの罪をなすりつけていると、小さな女の子に見抜かれた。
「今、その子が転んだのは、シオン殿下のせいじゃないわ。私、見ていたもの」
真っすぐにローレルを見つめる瞳に、少しだけ動揺した。しかし、すぐに冷静になり、女の子を人気《ひとけ》のないところへ連れて行き脅して解決した。
何も問題はない。ただ、少しだけ面白いなとは思った。そして、そんなつまらないことはすぐに忘れた。
女の子のことを思い出したのは、学園に『オルウェン伯爵家の娘が入学した』と聞いたときだった。
(オルウェン……。セリー商会を通じて裏社会に密接している、あのオルウェンか)
子どものころは裏社会のことまでは知らなかったが、オルウェン伯爵家はなかなか特殊な貴族だった。そのことに気がついているのは、ごくごく一部の王族と上位貴族だけだ。
(おしいことをしたな)
子どものころに出会ったあのお茶会の場で、オルウェンの娘リナリアを脅すのではなく口説いていれば利用できたのにと少しだけ後悔した。
(後悔? 私が?)
後悔している自身に驚いたが、そのときはそれだけだった。しかし、不思議なことに弟のシオンがリナリアに執着していた。
(相変わらず我が弟は愚かだな)
リナリアは、どこにでもいるような外見だし、突出して優秀なわけでもない。一度、群衆の中に紛れ込んでしまうと絶対に見つけられないような凡人だ。
(シオンは、リナリアを利用して、私と敵対でもするつもりか?)
確かにオルウェンという家柄だけは魅力的だが、王家を毛嫌いしているオルウェンと手を組むのは不可能だろう。
(シオン、もう少し私を楽しませてよ)
このままあまりにもつまらない日々が続くのなら、いっそのこと、この国ごと全部壊してしまいたくなる。
この国の初代国王は、各勢力が武力で争っている中、交渉だけで争いを終結させて一つの国へとまとめ上げた偉大な王だと言われている。
(だったら、私は、武力を使わず交渉だけで、この国の全てを壊してしまおうかな?)
ローレルは子どものころからずっと『初代王の再来』と言われているので、それくらいなら簡単にできそうだ。
(うん、そうしよう。私が学園を卒業するまでに面白いことが一つもおこらなければ、この国を壊そう)
そう決めてローレルは、学園生活を送っていた。五年間通い今年で卒業だが、未だに一つも面白いことが起こっていない。
だから、ローレルは自分から面白いことを探し始めた。今、一番面白そうなのは、リナリア=オルウェンだ。
シオンと付き合っているらしいので、シオンの振りをして近づいた。
リナリアの瞳を見てすぐに『二人の王子を見分けられている』と気がついた。なぜなら、リナリアの瞳には嫌悪が浮かんでいた。それは決して恋人に向けるものではない。
(私がローレルと分かっていて、こんな態度を取られたのは初めてだ)
ポッカリと空いた心の穴に、感じるはずのないかすかな痛みを感じた。
リナリアと手を繋ぐと、リナリアはまるで不快なものにさわられたように顔を青くしている。
(今、私がローレルと分かった上で、気持ち悪がられているんだ。リナリアは、私のことが気持ち悪いんだ)
試しにリナリアを抱きしめてみると、全力で嫌がられた。
(人って、私に媚びたり、私の機嫌をとったり、称賛したりする以外の行動もとるんだ! すごく、すごく面白いよ!)
リナリアは、二人の王子を見分けられることを必死に隠しているようで、ローレルに何をされても耐えている。
(どこまで耐えるの?)
試しにスカートの上からリナリアの太ももにふれると、リナリアは小さく息を吸った。悲鳴をあげるのを耐えているらしい。
(そんなに私のことが嫌?)
今までされたことのない反応が新鮮で面白すぎて胸がときめく。
「こんなに怯えて。リナリアは可愛いね」
この言葉は本心からだった。
(シオンがリナリアに執着する理由が、今、分かった)
自分を見分けてくれる人間がこんなにも嬉しいだなんて知らなかった。
(私もリナリアが欲しいよ。いつもみたいに、もらうねシオン)
ローレルはニッコリと微笑んだ。