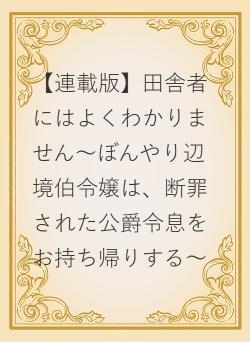シェリーの手記には、第三王子に裏切られたこと。自ら命を断とうと思い馬車に乗ってどこか遠くへ行こうとしていたときに、馬車が何者かに襲われたことが書かれていた。
乱暴に馬車の扉が開かれ、白銀の刃がシェリーに襲い掛かったが、シェリーは逃げもせず静かに目を閉じた。
いつまでたっても痛みを感じないで目を開くと、刃の先がシェリーの目の前で止まっていた。
顔を隠した黒ずくめの暗殺者をシェリーは無感情に見つめた。
「どうぞ」
かすかに暗殺者の身体が揺れた。そのあと、シェリーはなぜか気を失ってしまったそうだ。
そして、気がつけば、王宮の一室にも引けを取らない豪華な部屋のベッドに寝かされていて、黒髪の青年に保護されていたらしい。
シェリーがここはどこかと尋ねると、青年はベッドの側でひざまずいた。
そして、自分が第三王子の依頼でシェリーを暗殺しようとしていたことを語ってくれた。馬車を襲った黒ずくめの暗殺者は、この青年だったようだ。
「そうですか。私はかまいませんよ」
シェリーが元から死ぬつもりだったと青年に伝えると、青年は「だったらアンタのその命、俺にくれないか?」とひどく深刻そうに告げた。
青年の左頬には、大きな傷跡がある。その古傷のせいで、青年の表情は読み取りにくい。
「はい、お好きにどうぞ」
シェリーは自分で死ぬのも、この青年に殺されるのも一緒だと思っていたが、なぜかその日から青年に囲われて、シェリーは数え切れないほどの贈り物をもらうことになった。
今日も大きな花束を抱えて現れた青年に、シェリーは首をかしげた。
「いつになったら私を殺してくれるのですか?」
そう尋ねると、青年はいつもシェリーから顔をそらして「……アンタの命は俺のものだ」と不愉快そうな顔をする。
「でも、こんなにたくさん素敵なものをいただいて、毎日おいしい食事を与えられていると、いつか死にたくなくなるかもしれません」
「そ、そうか」
左頬にある大きな傷で分かりにくいが青年は笑ったようだ。
「私を殺さなくて良いのですか? 貴方は第三王子殿下に私の暗殺を依頼されたのですよね?」
シェリーが尋ねると、青年は口元をニヤリと歪めた。
「ああ、あの男か。安心しろ、もう王子ではないからな」
青年の言葉の意味が理解できず、シェリーは不思議そうに青年を見つめた。青年の頬が少しずつ赤くなっていくような気がする。
「アンタみたいなお綺麗なお姫様は知らないだろうが、俺はこれでも裏の世界では権力者なんだ。アンタを陥れた連中は一通り……な?」
何をしたのか聞いても青年はそれ以上教えてくれなかった。
「私を殺さないなら、貴方の目的は?」
しばらく黙り込んだ青年は、覚悟を決めたように口をひらいた。
「一度でいい……俺の名前を呼んでくれ」
**
リナリアはシェリーの手記を読みながら、胸をときめかせていた。
「お母様!」
「いいわよね!? ときめくわよね?」
母の言葉に激しく同意しながらリナリアはシェリーの手記を閉じた。まだ半分も読んでいないので、残りは自室でじっくりと読もうと決めた。
「ようするに、シェリー様は生きていて、第三王子や公爵令嬢たちは何らかの罰を受けたと言うことですね?」
「そうよ。そのころ、第三王子派閥の貴族が次々に変死してね。亡くなったシェリー様の呪いじゃないかってウワサになったそうよ。そのせいで、第三王子にかかわった貴族たちは他の貴族たちから避けられて、離縁されたり、次々に婚約破棄されたりしたそうよ」
「第三王子は?」
「この怪事件を引き越した張本人として、王族から除名され辺境に飛ばされたわ。でも、その道中で変死。その報を聞いた公爵令嬢は恐怖のあまり修道院に駆け込んで、懺悔しながら生涯、熱心に神に仕えて慈善活動をしながら過ごしたそうよ」
母の言葉を聞いて、リナリアは胸がスッとした。
「その一連の事件で、社交パーティーを出会いの場にすることも問題視されてね。今のように学園に通う仕組みができたってわけ」
「そうだったのですね」
過去にこんなことがあったのなら、オルウェン伯爵家が王家に利用されて捨てられたと言われるのも納得ができた。
本当は裏で凄惨な仕返しがされていたが、それはオルウェン伯爵家の人間しか知らないことなので、他の人から見ればオルウェン伯爵家は王族ともめ事を起こした落ち目の貴族だ。
母は優雅にお茶を一口飲んでから、「もう分かったと思うけど」と言った。
「その事件以来、オルウェン伯爵家は、王家とかかわりを持たないと決めたのよ。それができたのは、オルウェンがセリー商会と手を組んで手広く商売を始めたからなの」
セリー商会は、オルウェン伯爵家が出資しているこの国で一番大きな商会だった。商会を取り仕切っているのは、黒髪の男性だ。
そこでふと、リナリアは何かが引っ掛かった。
「黒髪? セリー……シェリー? お母様、もしかして、セリー商会は?」
母は優雅に微笑んだ。
「ご名答。暗殺者と結ばれたシェリー様の子孫が経営しているの。オルウェン伯爵家は、シェリー様の弟が継いでね。うちとセリー商会は実は親戚なのよ」
フフフと笑う母は楽しそうに「セリー商会って今でも裏社会に顔が聞くの」と小声で教えてくれた。
「だからね、リナリア。オルウェン伯爵家は王家に媚びないんじゃない。王家に媚びる必要がないのよ」
乱暴に馬車の扉が開かれ、白銀の刃がシェリーに襲い掛かったが、シェリーは逃げもせず静かに目を閉じた。
いつまでたっても痛みを感じないで目を開くと、刃の先がシェリーの目の前で止まっていた。
顔を隠した黒ずくめの暗殺者をシェリーは無感情に見つめた。
「どうぞ」
かすかに暗殺者の身体が揺れた。そのあと、シェリーはなぜか気を失ってしまったそうだ。
そして、気がつけば、王宮の一室にも引けを取らない豪華な部屋のベッドに寝かされていて、黒髪の青年に保護されていたらしい。
シェリーがここはどこかと尋ねると、青年はベッドの側でひざまずいた。
そして、自分が第三王子の依頼でシェリーを暗殺しようとしていたことを語ってくれた。馬車を襲った黒ずくめの暗殺者は、この青年だったようだ。
「そうですか。私はかまいませんよ」
シェリーが元から死ぬつもりだったと青年に伝えると、青年は「だったらアンタのその命、俺にくれないか?」とひどく深刻そうに告げた。
青年の左頬には、大きな傷跡がある。その古傷のせいで、青年の表情は読み取りにくい。
「はい、お好きにどうぞ」
シェリーは自分で死ぬのも、この青年に殺されるのも一緒だと思っていたが、なぜかその日から青年に囲われて、シェリーは数え切れないほどの贈り物をもらうことになった。
今日も大きな花束を抱えて現れた青年に、シェリーは首をかしげた。
「いつになったら私を殺してくれるのですか?」
そう尋ねると、青年はいつもシェリーから顔をそらして「……アンタの命は俺のものだ」と不愉快そうな顔をする。
「でも、こんなにたくさん素敵なものをいただいて、毎日おいしい食事を与えられていると、いつか死にたくなくなるかもしれません」
「そ、そうか」
左頬にある大きな傷で分かりにくいが青年は笑ったようだ。
「私を殺さなくて良いのですか? 貴方は第三王子殿下に私の暗殺を依頼されたのですよね?」
シェリーが尋ねると、青年は口元をニヤリと歪めた。
「ああ、あの男か。安心しろ、もう王子ではないからな」
青年の言葉の意味が理解できず、シェリーは不思議そうに青年を見つめた。青年の頬が少しずつ赤くなっていくような気がする。
「アンタみたいなお綺麗なお姫様は知らないだろうが、俺はこれでも裏の世界では権力者なんだ。アンタを陥れた連中は一通り……な?」
何をしたのか聞いても青年はそれ以上教えてくれなかった。
「私を殺さないなら、貴方の目的は?」
しばらく黙り込んだ青年は、覚悟を決めたように口をひらいた。
「一度でいい……俺の名前を呼んでくれ」
**
リナリアはシェリーの手記を読みながら、胸をときめかせていた。
「お母様!」
「いいわよね!? ときめくわよね?」
母の言葉に激しく同意しながらリナリアはシェリーの手記を閉じた。まだ半分も読んでいないので、残りは自室でじっくりと読もうと決めた。
「ようするに、シェリー様は生きていて、第三王子や公爵令嬢たちは何らかの罰を受けたと言うことですね?」
「そうよ。そのころ、第三王子派閥の貴族が次々に変死してね。亡くなったシェリー様の呪いじゃないかってウワサになったそうよ。そのせいで、第三王子にかかわった貴族たちは他の貴族たちから避けられて、離縁されたり、次々に婚約破棄されたりしたそうよ」
「第三王子は?」
「この怪事件を引き越した張本人として、王族から除名され辺境に飛ばされたわ。でも、その道中で変死。その報を聞いた公爵令嬢は恐怖のあまり修道院に駆け込んで、懺悔しながら生涯、熱心に神に仕えて慈善活動をしながら過ごしたそうよ」
母の言葉を聞いて、リナリアは胸がスッとした。
「その一連の事件で、社交パーティーを出会いの場にすることも問題視されてね。今のように学園に通う仕組みができたってわけ」
「そうだったのですね」
過去にこんなことがあったのなら、オルウェン伯爵家が王家に利用されて捨てられたと言われるのも納得ができた。
本当は裏で凄惨な仕返しがされていたが、それはオルウェン伯爵家の人間しか知らないことなので、他の人から見ればオルウェン伯爵家は王族ともめ事を起こした落ち目の貴族だ。
母は優雅にお茶を一口飲んでから、「もう分かったと思うけど」と言った。
「その事件以来、オルウェン伯爵家は、王家とかかわりを持たないと決めたのよ。それができたのは、オルウェンがセリー商会と手を組んで手広く商売を始めたからなの」
セリー商会は、オルウェン伯爵家が出資しているこの国で一番大きな商会だった。商会を取り仕切っているのは、黒髪の男性だ。
そこでふと、リナリアは何かが引っ掛かった。
「黒髪? セリー……シェリー? お母様、もしかして、セリー商会は?」
母は優雅に微笑んだ。
「ご名答。暗殺者と結ばれたシェリー様の子孫が経営しているの。オルウェン伯爵家は、シェリー様の弟が継いでね。うちとセリー商会は実は親戚なのよ」
フフフと笑う母は楽しそうに「セリー商会って今でも裏社会に顔が聞くの」と小声で教えてくれた。
「だからね、リナリア。オルウェン伯爵家は王家に媚びないんじゃない。王家に媚びる必要がないのよ」