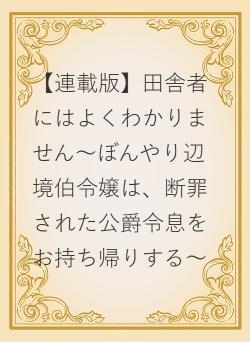この学園からサジェスは去って行った。
学園内でサジェスを避けるように過ごす必要がなくなったので、リナリアはのんびりと穏やかな日々を過ごすことができた。
(ものすごく平和だわ……)
教室の窓から差し込む日差しの温かさが、リナリアの眠気を誘う。授業中の先生の声を聞き流しながら、リナリアは、先日の母の言葉を思い出していた。
――それって本当に友達なの?
――だったら向こうの片思いなのね
――リナリアの花言葉はね「この恋に気づいて」よ。
(お母様ったら、シオンが私に片思いをしているだなんて……そんなことあるはずが……)
不思議と『あるはずがない』と言い切れない自分がいた。『私なんか』という卑下する気持ちを一度横に置いて、リナリアはこれまでのシオンの言動を静かに思い出してみた。
(罰ゲームかと思っていたら、そうじゃないってシオンに言われて、『ずっと見守っていた』とか、『子どもの頃に初めてお茶会で会ったときから好きだった』とか言われたような?)
あのときは、そんなことがあるはずがないと思っていた。そして、シオンが『恋多き男』だということを思い出し、『あれは女性を喜ばせるための冗談だったのね』ということでリナリアは納得した。
(もし、あのときのシオンの言葉が冗談じゃなかったら……?)
シオンの悪評は全てローレルにより作られたウソだ。だったら、『恋多き男』というウワサもウソの可能性もある。
(でも、もしそうだとしたら、シオンと私は一目惚れ同士で、シオンは子どもの頃からずっと私のことが好きだったということになってしまうんだけど……そ、そんなに都合の良いことがあるの?)
信じたい気持ちと信じてしまうのが怖い気持ちの間で、ずっと揺れ動いている。
(シオンに聞けたらいいのに……)
シオンに直接『どうして、私にリナリアの花をくれるの?』と聞いてしまいたかった。
(でもね……)
例えシオンの答えがどうであれ、リナリアがシオンと結ばれることはない。それは、元から分かっていたことだが、母の話を聞いてより深く確信した。
あの日、リナリアの花言葉が『この恋に気づいて』だと教えてくれた母は、「この花はね、片思いの相手に自分の恋心を気づいてほしくて送る花なのよ」と言葉を続けた。
「では、お父様がお母様にリナリアの花を贈っていたのは、お父様からお母様へのアプローチだったんですか?」
母は、「そうよ。分かりにくいわよねぇ」と笑う。
「その当時の私は、貴女と同じでリナリアの花言葉なんて知らなかったから、あの人の気持ちにまったく気がつかなかったのよね。懐かしいわ」
ちなみに結婚後の父は、記念日があるたびに、母に赤い薔薇の花束を贈っている。
「お母様、もしかして赤い薔薇の花言葉は……?」
「愛しています、よ」
普段は口数が少なく、気難しそうな父の意外な一面を知ってしまった。
「……お父様って意外とロマンチストだったんですね」
母は、「それで? これは誰からの贈り物なの?」と嬉しそうにリナリアに尋ねる。
「それは……。でも、本当にただの友達なんです。リナリアの花も偶然で……」
「そうなの? そうだったとしても、私は毎朝、娘に花を贈ってくれる人が誰なのか知りたいわ」
リナリアがためらっていると、母は「そういえば、さっき止まっていた馬車の紋章、黒百合だったわよね」と呟いた。
「黒百合は王家の紋章ね。ま、まさか……貴女、どちらかの殿下と!?」
困ったリナリアは観念して「はい、そのお花は、第二王子のシオン殿下からいただきました」と白状した。
淑女らしくなく、あんぐりと口を開けた母は、「ちょ、ちょっと座って話しましょうか」と言いながら、側にいたメイドにお茶の準備を頼んだ。
なぜか母は、父の書斎にお茶を運ばせた。書斎のソファーに向かい合って座ると、母からは深いため息が聞こえてくる。
「本当にシオン殿下からリナリアの花をもらっているの?」
「はい」
「なるほど……。だから、急にオルウェン伯爵家と王族の過去を聞きたがったのね。リナリアは、どこまで知っているの?」
母の深刻そうな表情から、両家の関係が良くないことが分かる。
「私は何も知りません。ただ、ある人から『利用されて捨てられたオルウェン伯爵家』って言われたんです。オルウェンなら王家に媚びない理由も分かるって」
第一王子ローレルに言われた言葉の意味は未だに分からない。
立ち上がった母は、父の書斎の本棚から一冊の本を引き抜いた。ソファーに座り直した母は、テーブルにその本を置く。
「これはね、数十年前にオルウェン伯爵家の長女に生まれた方が書いた手記《しゅき》なの」
「手記?」
「手記は、自分が経験したり、体験したりしたことを書き記したもののことよ。だから、ここには、その方の身に起こったことがその方本人の手で書かれているわ」
「もしかして……」
リナリアが母を見ると、母は小さく頷いた。
「ここには、その方がいかに王家に利用されて捨てられたかが書かれているの」
学園内でサジェスを避けるように過ごす必要がなくなったので、リナリアはのんびりと穏やかな日々を過ごすことができた。
(ものすごく平和だわ……)
教室の窓から差し込む日差しの温かさが、リナリアの眠気を誘う。授業中の先生の声を聞き流しながら、リナリアは、先日の母の言葉を思い出していた。
――それって本当に友達なの?
――だったら向こうの片思いなのね
――リナリアの花言葉はね「この恋に気づいて」よ。
(お母様ったら、シオンが私に片思いをしているだなんて……そんなことあるはずが……)
不思議と『あるはずがない』と言い切れない自分がいた。『私なんか』という卑下する気持ちを一度横に置いて、リナリアはこれまでのシオンの言動を静かに思い出してみた。
(罰ゲームかと思っていたら、そうじゃないってシオンに言われて、『ずっと見守っていた』とか、『子どもの頃に初めてお茶会で会ったときから好きだった』とか言われたような?)
あのときは、そんなことがあるはずがないと思っていた。そして、シオンが『恋多き男』だということを思い出し、『あれは女性を喜ばせるための冗談だったのね』ということでリナリアは納得した。
(もし、あのときのシオンの言葉が冗談じゃなかったら……?)
シオンの悪評は全てローレルにより作られたウソだ。だったら、『恋多き男』というウワサもウソの可能性もある。
(でも、もしそうだとしたら、シオンと私は一目惚れ同士で、シオンは子どもの頃からずっと私のことが好きだったということになってしまうんだけど……そ、そんなに都合の良いことがあるの?)
信じたい気持ちと信じてしまうのが怖い気持ちの間で、ずっと揺れ動いている。
(シオンに聞けたらいいのに……)
シオンに直接『どうして、私にリナリアの花をくれるの?』と聞いてしまいたかった。
(でもね……)
例えシオンの答えがどうであれ、リナリアがシオンと結ばれることはない。それは、元から分かっていたことだが、母の話を聞いてより深く確信した。
あの日、リナリアの花言葉が『この恋に気づいて』だと教えてくれた母は、「この花はね、片思いの相手に自分の恋心を気づいてほしくて送る花なのよ」と言葉を続けた。
「では、お父様がお母様にリナリアの花を贈っていたのは、お父様からお母様へのアプローチだったんですか?」
母は、「そうよ。分かりにくいわよねぇ」と笑う。
「その当時の私は、貴女と同じでリナリアの花言葉なんて知らなかったから、あの人の気持ちにまったく気がつかなかったのよね。懐かしいわ」
ちなみに結婚後の父は、記念日があるたびに、母に赤い薔薇の花束を贈っている。
「お母様、もしかして赤い薔薇の花言葉は……?」
「愛しています、よ」
普段は口数が少なく、気難しそうな父の意外な一面を知ってしまった。
「……お父様って意外とロマンチストだったんですね」
母は、「それで? これは誰からの贈り物なの?」と嬉しそうにリナリアに尋ねる。
「それは……。でも、本当にただの友達なんです。リナリアの花も偶然で……」
「そうなの? そうだったとしても、私は毎朝、娘に花を贈ってくれる人が誰なのか知りたいわ」
リナリアがためらっていると、母は「そういえば、さっき止まっていた馬車の紋章、黒百合だったわよね」と呟いた。
「黒百合は王家の紋章ね。ま、まさか……貴女、どちらかの殿下と!?」
困ったリナリアは観念して「はい、そのお花は、第二王子のシオン殿下からいただきました」と白状した。
淑女らしくなく、あんぐりと口を開けた母は、「ちょ、ちょっと座って話しましょうか」と言いながら、側にいたメイドにお茶の準備を頼んだ。
なぜか母は、父の書斎にお茶を運ばせた。書斎のソファーに向かい合って座ると、母からは深いため息が聞こえてくる。
「本当にシオン殿下からリナリアの花をもらっているの?」
「はい」
「なるほど……。だから、急にオルウェン伯爵家と王族の過去を聞きたがったのね。リナリアは、どこまで知っているの?」
母の深刻そうな表情から、両家の関係が良くないことが分かる。
「私は何も知りません。ただ、ある人から『利用されて捨てられたオルウェン伯爵家』って言われたんです。オルウェンなら王家に媚びない理由も分かるって」
第一王子ローレルに言われた言葉の意味は未だに分からない。
立ち上がった母は、父の書斎の本棚から一冊の本を引き抜いた。ソファーに座り直した母は、テーブルにその本を置く。
「これはね、数十年前にオルウェン伯爵家の長女に生まれた方が書いた手記《しゅき》なの」
「手記?」
「手記は、自分が経験したり、体験したりしたことを書き記したもののことよ。だから、ここには、その方の身に起こったことがその方本人の手で書かれているわ」
「もしかして……」
リナリアが母を見ると、母は小さく頷いた。
「ここには、その方がいかに王家に利用されて捨てられたかが書かれているの」