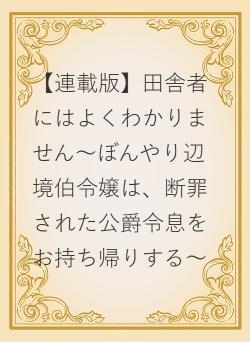リナリアは、朝の身支度を終えて制服に身を包み、いつものように馬車に揺られて学園へと向かった。
(昨日、いろんなことがありすぎて、シオン殿下にどんな顔で会ったらいいのか分からないわ)
帰りの馬車の中で、シオンに子どものころからリナリアのことが好きだったと言われたが、現実味がなさすぎてその言葉を素直に信じることはできない。
(とにかく、今はお優しいシオン殿下の悪評をなんとかしないと!)
そこでふとリナリアは、シオンのウワサの中に『恋多き男』というものがあったことを思い出した。
(あ、そっか。シオン殿下ほどのお方になると、女性を喜ばせるためにああいう冗談を言ってくださるのかもしれない!)
男性に免疫がないので思いっきり動揺してしまったが、『まぁ、お上手だこと。フフッ』とか言いながら、サラリと流すのが正しい対応だったのかもしれない。
(私ったら、殿下のご冗談を本気にして恥ずかしいわ……!)
リナリアが反省しながら馬車から降りると、少し離れたところに生徒たちの人だかりができていた。その中心には、王家の紋章黒百合の花が描かれた馬車が止まっている。
その馬車から降りてきたのは、輝く金髪に紫色の瞳を持った王子様だった。人だかりの中から歓声が上がったが、リナリアの心は少しもときめかない。
(根性悪(こんじょうわる)のローレル)
ローレルを取り囲んだ生徒たちは、我先にとローレルに挨拶をした。生徒たちから挨拶と共に降り注ぐような賛辞を浴びながら、ローレルは爽やかな笑みを浮かべている。
(こう見るとウソ臭い笑顔ね)
リナリアが、そんなことを思っていると、ふとローレルがこちらを見たので慌てて視線をそらした。
ローレルへの賛辞は、本来ならシオンが受けるべきものだ。ローレルのせいで、シオンは今もいわれのない中傷を受けている。
そのことを早くシオンに伝えたかったが、学園内で堂々とシオンに声をかけることはできない。リナリアは、ソワソワしながら放課後になるのを待った。昨日、別れ際にシオンが『また明日ね』と言ったので、放課後になるといつものように護衛のゼダが迎えに来ると予想できた。
リナリアの予想通りに、全ての授業が終わるとゼダが迎えに来てくれた。
「お迎えにあがりました。リナリ……」
「行きます!」
リナリアが前のめりになりながら伝えると、いつも淡々としているゼダが珍しく驚いていた。その場に居合わせた友人ケイトは、嬉しそうに「ふふっ、いつも仲良しね。行ってらっしゃい」と手を振ってくれる。
(ケイトは、私とゼダ様が付き合っているって勘違いしているのよね)
『この誤解もいつか解かないと』と思ったが、とにかく今はシオンに会いたかった。サロンにたどり着くと、いつも通りにシオンがわざわざソファーから立ち上がって出迎えてくれた。
どこか儚げな表情を浮かべているシオンは、「リナリア、来てくれて嬉しいよ」と言いながら、ホッと胸をなでおろした。その仕草があまりに優雅で見とれてしまう。
(……はっ!? 今は殿下の美しさに、見とれている場合ではないわ!)
ソファーに座る間もなく、リナリアはシオンに詰め寄った。
「殿下、どうしても聞いていただきたいお話があります!」
ニッコリと微笑んだシオンは「殿下じゃなくて、シオンだよ」と、のんきなことを言っている。
(ああっもう……控えめにいってシオン殿下は大天使様のようだわ!!)
昨日の帰りの馬車で感じた悪寒のようなものは、きっと気のせいだったのだろう。
「あの、シオン殿下!」
「シオン、だよ」
シオンはニコニコと微笑みながら少しも譲ろうとしない。このままでは、話がまったく進まないのでリナリアは覚悟を決めた。
「……その、シ、シオン……」
シオンは嬉しそうに微笑むと「なぁに、リナリア」と甘えるような声を出す。心臓がもたないので、リナリアはシオンから距離を取りながら話し始めた。
「実は、私、過去にお茶会であったことを思い出したんです」
「それって、リナリアと私が出会ったあのお茶会のこと?」
リナリアが頷くと、シオンは「もしかして、私と出会ったことを今まで忘れていたの?」と悲しそうな顔をする。
「違いますっ!? シオン殿下とのことは全て覚えています! そうではなくて、ローレル殿下のことです」
リナリアが『ローレル』と口にしたとたんに、シオンの美しい紫色の瞳がスッと細くなった。
「ローレルがどうかしたの?」
そう言ったシオンは、相変わらず優しい声音で口元は微笑んでいるが、目が少しも笑っていない。『美人が怒ると迫力がある』というのはこういうことを言うのかもしれない。
「あの、えっと、その……。まだ子どもだった私は恐怖のせいか、あのお茶会のときにローレル殿下に脅されたことを今まで忘れてしまっていたのです。シオン殿下の悪評を流しているのは、ローレル殿下です。ローレル殿下がシオン殿下を陥れようとしているのです」
シオンは憂いを帯びた表情でリナリアから顔をそむけた。こんな緊迫した状況なのに、シオンの首筋に色気を感じてドキッとしてしまう。
(こんなときにまで、いやらしい目で見てすみません、殿下……)
リナリアが申し訳ない気持ちでいっぱいになっていると、シオンは消えそうな声でリナリアの名前を呼んだ。
「リナリア……」
優しいシオンを残酷な真実で傷つけてしまった。リナリアがどう慰めたらいいのか悩みながら右腕をそっとシオンに伸ばすと、シオンは両手でリナリアの右手を握りしめた。
「ひどいよ、リナリア」
「申し訳ありません、シオン殿下。ローレル殿下が犯人で信じられないのは分かりますが……」
シオンは握りしめていたリナリアの右手にそっと自分の左頬を押し当てた。そのとたんに、リナリアはたった今、シオンに伝えようとしていた言葉が全て吹き飛んだ。
(えっ!? やわらかっ!? 何、この陶磁器のように白く滑らかな殿下のお肌は!?)
リナリアが本気でシオンにお肌のお手入れの仕方を聞こうか悩んでいると、シオンは「私のことは『シオンと呼んで』とお願いしているのに」と悲しそうに呟く。
「あ、すみません」
リナリアが素直に謝罪すると、シオンはため息をついた。
「お願いするだけじゃダメみたいだね。次にリナリアが私のことを『シオン』と呼ばなかったら、どうしよう……お仕置きが必要かな?」
(ああ、思案する殿下も麗しいわ……いや、違う違う! 今は殿下の悪評をなんとかしないと!)
シオンの手からリナリアが右手を引き抜くと、シオンはとても残念そうな顔をした。
(昨日、いろんなことがありすぎて、シオン殿下にどんな顔で会ったらいいのか分からないわ)
帰りの馬車の中で、シオンに子どものころからリナリアのことが好きだったと言われたが、現実味がなさすぎてその言葉を素直に信じることはできない。
(とにかく、今はお優しいシオン殿下の悪評をなんとかしないと!)
そこでふとリナリアは、シオンのウワサの中に『恋多き男』というものがあったことを思い出した。
(あ、そっか。シオン殿下ほどのお方になると、女性を喜ばせるためにああいう冗談を言ってくださるのかもしれない!)
男性に免疫がないので思いっきり動揺してしまったが、『まぁ、お上手だこと。フフッ』とか言いながら、サラリと流すのが正しい対応だったのかもしれない。
(私ったら、殿下のご冗談を本気にして恥ずかしいわ……!)
リナリアが反省しながら馬車から降りると、少し離れたところに生徒たちの人だかりができていた。その中心には、王家の紋章黒百合の花が描かれた馬車が止まっている。
その馬車から降りてきたのは、輝く金髪に紫色の瞳を持った王子様だった。人だかりの中から歓声が上がったが、リナリアの心は少しもときめかない。
(根性悪(こんじょうわる)のローレル)
ローレルを取り囲んだ生徒たちは、我先にとローレルに挨拶をした。生徒たちから挨拶と共に降り注ぐような賛辞を浴びながら、ローレルは爽やかな笑みを浮かべている。
(こう見るとウソ臭い笑顔ね)
リナリアが、そんなことを思っていると、ふとローレルがこちらを見たので慌てて視線をそらした。
ローレルへの賛辞は、本来ならシオンが受けるべきものだ。ローレルのせいで、シオンは今もいわれのない中傷を受けている。
そのことを早くシオンに伝えたかったが、学園内で堂々とシオンに声をかけることはできない。リナリアは、ソワソワしながら放課後になるのを待った。昨日、別れ際にシオンが『また明日ね』と言ったので、放課後になるといつものように護衛のゼダが迎えに来ると予想できた。
リナリアの予想通りに、全ての授業が終わるとゼダが迎えに来てくれた。
「お迎えにあがりました。リナリ……」
「行きます!」
リナリアが前のめりになりながら伝えると、いつも淡々としているゼダが珍しく驚いていた。その場に居合わせた友人ケイトは、嬉しそうに「ふふっ、いつも仲良しね。行ってらっしゃい」と手を振ってくれる。
(ケイトは、私とゼダ様が付き合っているって勘違いしているのよね)
『この誤解もいつか解かないと』と思ったが、とにかく今はシオンに会いたかった。サロンにたどり着くと、いつも通りにシオンがわざわざソファーから立ち上がって出迎えてくれた。
どこか儚げな表情を浮かべているシオンは、「リナリア、来てくれて嬉しいよ」と言いながら、ホッと胸をなでおろした。その仕草があまりに優雅で見とれてしまう。
(……はっ!? 今は殿下の美しさに、見とれている場合ではないわ!)
ソファーに座る間もなく、リナリアはシオンに詰め寄った。
「殿下、どうしても聞いていただきたいお話があります!」
ニッコリと微笑んだシオンは「殿下じゃなくて、シオンだよ」と、のんきなことを言っている。
(ああっもう……控えめにいってシオン殿下は大天使様のようだわ!!)
昨日の帰りの馬車で感じた悪寒のようなものは、きっと気のせいだったのだろう。
「あの、シオン殿下!」
「シオン、だよ」
シオンはニコニコと微笑みながら少しも譲ろうとしない。このままでは、話がまったく進まないのでリナリアは覚悟を決めた。
「……その、シ、シオン……」
シオンは嬉しそうに微笑むと「なぁに、リナリア」と甘えるような声を出す。心臓がもたないので、リナリアはシオンから距離を取りながら話し始めた。
「実は、私、過去にお茶会であったことを思い出したんです」
「それって、リナリアと私が出会ったあのお茶会のこと?」
リナリアが頷くと、シオンは「もしかして、私と出会ったことを今まで忘れていたの?」と悲しそうな顔をする。
「違いますっ!? シオン殿下とのことは全て覚えています! そうではなくて、ローレル殿下のことです」
リナリアが『ローレル』と口にしたとたんに、シオンの美しい紫色の瞳がスッと細くなった。
「ローレルがどうかしたの?」
そう言ったシオンは、相変わらず優しい声音で口元は微笑んでいるが、目が少しも笑っていない。『美人が怒ると迫力がある』というのはこういうことを言うのかもしれない。
「あの、えっと、その……。まだ子どもだった私は恐怖のせいか、あのお茶会のときにローレル殿下に脅されたことを今まで忘れてしまっていたのです。シオン殿下の悪評を流しているのは、ローレル殿下です。ローレル殿下がシオン殿下を陥れようとしているのです」
シオンは憂いを帯びた表情でリナリアから顔をそむけた。こんな緊迫した状況なのに、シオンの首筋に色気を感じてドキッとしてしまう。
(こんなときにまで、いやらしい目で見てすみません、殿下……)
リナリアが申し訳ない気持ちでいっぱいになっていると、シオンは消えそうな声でリナリアの名前を呼んだ。
「リナリア……」
優しいシオンを残酷な真実で傷つけてしまった。リナリアがどう慰めたらいいのか悩みながら右腕をそっとシオンに伸ばすと、シオンは両手でリナリアの右手を握りしめた。
「ひどいよ、リナリア」
「申し訳ありません、シオン殿下。ローレル殿下が犯人で信じられないのは分かりますが……」
シオンは握りしめていたリナリアの右手にそっと自分の左頬を押し当てた。そのとたんに、リナリアはたった今、シオンに伝えようとしていた言葉が全て吹き飛んだ。
(えっ!? やわらかっ!? 何、この陶磁器のように白く滑らかな殿下のお肌は!?)
リナリアが本気でシオンにお肌のお手入れの仕方を聞こうか悩んでいると、シオンは「私のことは『シオンと呼んで』とお願いしているのに」と悲しそうに呟く。
「あ、すみません」
リナリアが素直に謝罪すると、シオンはため息をついた。
「お願いするだけじゃダメみたいだね。次にリナリアが私のことを『シオン』と呼ばなかったら、どうしよう……お仕置きが必要かな?」
(ああ、思案する殿下も麗しいわ……いや、違う違う! 今は殿下の悪評をなんとかしないと!)
シオンの手からリナリアが右手を引き抜くと、シオンはとても残念そうな顔をした。