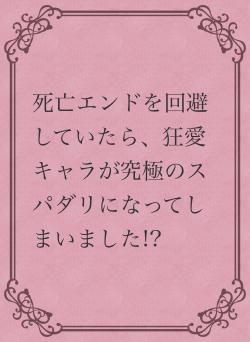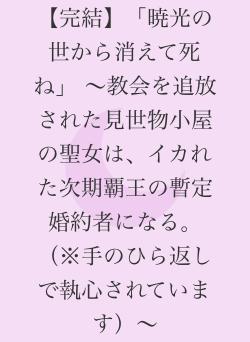力を貸してやると言われた。
あまりにも急なことで聞き間違いかと思い、サルヴァドールにもう一度確認をとる。
「本当に、本当に手伝ってくれる?」
『ああ。その前に、オレの封印を解いてくれたらな』
「封印って。あれ、まだ解かれてないの?」
『まだ? お前……悪魔やら契約のことも知ったふうだったよな。何者だ?』
「え、え〜、そうかな」
疑わしげな声に、私は口に手を当てた。
『その動き、なにか隠してるヤツがする動きだ。お前、一体なんなんだ』
「そ、それはサルヴァがちゃんと協力してくれるって確証がもてたら話す!」
『ガキの癖に変なところで言葉がしっかりしてるよな』
まずい、どんどん疑念を抱き始めている。
「今大切なのは、サルヴァのことだよ」
逸れていた軌道を無理やり修正して、封印についての話に戻した。
私が知っている「リデルの歌声」のサルヴァドールの封印は、まず第一章の黒幕であるクリストファーと契約した悪魔を歌で退ける。
そして、歌に込められた効果によりサルヴァドールの封印が解かれる、という流れだったはず。
ある理由で、リデルは公爵領に拉致されるんだよね。ちょうど閉じ込められる場所が別館の書庫室にある倉庫で、その流れで本に封印されていたサルヴァドールにも歌が聞こえるのだ。
「封印って、どうやったら解けるの?」
『古の天使が残した歌を聞けば、解けるはずだ。オレの封印は同じ大悪魔にやられてもんだからな』
「それ、わたしじゃできないじゃん……わたしが知ってるの、旋律だけだよ」
『だから中途半端なんだってさっき言っただろ。動けるようにはなったが、ほかはさっぱりだ』
だからサルヴァドールは本のままなんだ。彼は他の大悪魔によって本の中に封印されたので、封印を完全に解かないと本体が閉じ込められたままということだった。
リデルはちゃんと歌ってたもんな。サルヴァドールって、急に出てくるキャラだったから封印が解かれた描写なんて一つもなかったし。
「ほかにないのかな、封印が解ける方法」
『お前じゃ魔力も少ねぇから、取り込んだところで大した力に変えられないしな、核もしょぼい。あとは、魂を取り込むぐらいしか思いつかない』
「魂を取り込む……」
『普通の人間は魂を取られたら死ぬんだよ。だが、お前は特殊だ。なぜか知らないが二つあるからな。天使の気配がして不自然に体から浮いているそっちの魂をオレにくれるなら、封印は解ける……たぶん』
私のような体の人間は今まで目にしたことがなかったようで、サルヴァドールも断言はしなかった。
封印を解く方法について整理してみる。
まず、私では歌声が使えないのでこのやり方は一番初めに除外。
つづいて魂を取り込む方法は、ただの魂ではなく、天使の気配――名残りがあるものじゃないと意味がない。
どうやら私には魂が二つあり、サルヴァドールの封印が解ける可能性があるとすれば、おそらく前世の私のものである魂を取り込むということ。
「わたしは魂が二つあるから、一つサルヴァにあげても、大丈夫ってことだよね? おかしくならないよね?」
『理屈で考えるならな。実際のところやってみないとわからない』
「それもそうだ……」
不安だけど、もうこれに賭けるしかない気がする。ほかに宛になるような人を知らないし、何よりも悩んでいる時間すら惜しい。
うじうじと選択を躊躇っていては、それこそ手遅れになりかねないから。
「わかった、お願いします。それで、サルヴァの力を貸して」
サルヴァドールは「リデルの歌声」の登場キャラの中でも謎が多かった。
大悪魔だというわりには、人間の核には興味ないし、むしろそこら辺の人間に取り憑く悪魔を退治しようとするし。
エピローグまで読み終えても、サルヴァドールはリデルの相棒ポジションで、マスコット的なキャラクターのままだった。
わからない部分は多々あるけれど、普通の悪魔とは違う。
私を騙して乗っ取ろうだとか、核を喰らってやるだとか、そんなことは考えない――と、信じたい。
『よし、いいんだな』
その問いに、何度も頷く。
もう腹を決めてやるしかないのだ。
どうやって私の中から魂を取るんだろうと思っていれば、ずっと目の前を浮遊していた本が、黄金の光を帯び始めた。
光というか、靄に近いかもしれない。靄に光を纏わせた感じ。
その黄金に光る靄は、スっと本から伸びて私の全身を包み込む。
最初は慣れない感覚に身を固くしていたけれど、そのうち平気になってきて、ゆっくりと瞼を下ろした。
『バカ素直なやつ』
耳を掠めたサルヴァドールの声。意外そうでいて、ひどくおかしそうに、思わず笑ってしまったような声だった。
***
「おい」
「…………」
「おい」
「……む、ん?」
「もう目ぇ開けろ。終わった」
抜き取られたような感覚もなく拍子抜けしてしまう。
ぎしりとベッドが軋む音がして、私は声の通りに目を開く。
視界に飛び込んできたのは、じとーっとまるで猫のような瞳で私を見つめる少年の顔だった。
「…………え、だれっ」
「オレ」
「だから、だれ……?」
「本当にわからないのか?」
私の様子に不敵な笑みを携えた少年は、口角を吊り上げて試すような眼差しを向けてくる。
昨夜出会ったゼノと匹敵するくらいの美少年だ。
無造作な黒髪と金の瞳。まつ毛は長さのあまり目尻にまでかかっていて。見た目もゼノと同じくらいで、ベッドの端に座り体を後ろにひねるような体勢で私の顔を覗き込んでいる。
「サ、サルヴァ?」
「あたり」
「ど、どうして!? 人だったの!?」
ようやく現実のものだと頭が理解し、たまらず声をあげた。
私の知っているサルヴァドールは、鳥か狐のような姿の二動物にしか変化していなかった。
基本は狐よりの姿をしており、人の姿になるだなんて「リデルの歌声」でもなかったのに。
「人じゃなくて、悪魔な。大悪魔ともなれば、人型にだってなれるんだよ」
(ノベルゲームの中では一度も人の姿じゃなかったけど!?)
サルヴァドールは自分の前髪を指で弄って遊んでいる。
横から見ても整った顔をしている。どうしてこれを公式で見られなかったのか不思議なくらいだ。
「そんなにオレの人型が気に入らないのか?」
「逆だよ、どうしてそんなにかっこいいの?」
これではマスコットキャラという立場では収まらない。私の知らない公式供給があったのだろうか。今ではわからないことだけど、本当にびっくりした。
思ったままの意見をさらけ出した私に、サルヴァドールは満更でもない顔をしている。
「ま、オレは大悪魔サルヴァドール様だからな。欠点なんてないんだよ」
得意げに笑う。様になっているのがすごい。
子供の姿なのに、色気まで兼ね備えているなんて。
「にしても、お前って別の世界の人間だったのか」
「へ……」
「魂を取り込んだら、なんとなく記憶が入ってきてな。どーりで悪魔とか契約を知ってるわけだ」
さらりと言ってのけるので、私は言葉を失った。
「どっちもお前の魂だったからか、必然的に繋がったみたいだな。契約印、左手の甲にあるだろ」
指摘されて自分の左手に注目すると、たしかに契約の印である紋様が刻まれていた。