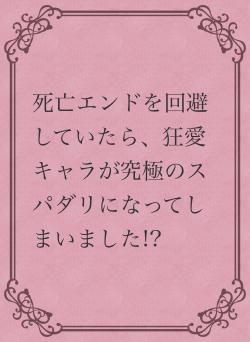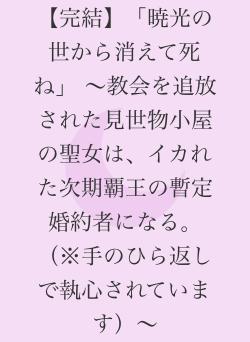目覚めたとき、もう何度も見た天井でほっとする。
でも、なぜだか体が重くて思うように動けなかった。
なんとか上体を起こして、背中に枕を置いて寄りかかる。
それからしばらくぼうっと過ごしたあとで、書庫室でのことを思い出した。
付き合ってもらったゼノに悪いことをしてしまった。私は倒れたあと、どうやって部屋に戻ったのだろう。
『よう、目が覚めたか』
「わあっ」
いきなり話しかけられ、短い叫び声をあげる。
目線の先には古びた本がふわふわと浮かんでいて、その本が私に声をかけているのだ。
『おい、まだ寝ぼけてるのか? お前がオレを呼び起こしたんだろ』
「そう、だけど」
たしかに私が探し求めていたのは、この本である。
まさか本当に現れてくれるとは思わなくてつい反応が遅れてしまう。
それに私の前世の記憶が正しければ、この本は別の姿に変化できたはずなのだけど。
本から言葉が聞こえるのって、かなりシュールである。
『なんだ? どうした? また固まってるな』
「あの、名前を教えてもらっても……」
『あん? 仕方ねー教えてやる。よーく胸に刻み込めよ。オレの名は、サルヴァドール。大悪魔のサルヴァドール様だ』
本はパタパタと開閉を繰り返しながら得意げな声で語る。
私は心の中でガッツポーズを決めながら、目線の斜め上を飛んでいるサルヴァドールを見上げた。
大悪魔、サルヴァドール。
彼は「リデルの歌声」で、第一章の終盤に出てくるキャラクターだった。
別の大悪魔によって本の中に封印されていたところを、リデルの歌声によって自由の身となり、それからはリデルの良き相棒として物語に登場していた。
つまり、本来ならヒロインが見つけだすところを、私が先を越して鼻歌で釣ってしまったのである。
リデルには申し訳ないけれど、私も命がかかっているのでやれるだけのことはやるつもりだ。サルヴァドールを呼び出したのも、もちろんそのためだった。
だけど、おかしいな。
サルヴァドールは普段リデルと共に行動をするとき、動きやすいように動物に姿を変えていたのに。
『さっきからなに難しい顔してるんだよ、ガキのくせに』
「ねえ、どうして本なの?」
『は、なに?』
「もっとほかの姿に変身とか〜、できない?」
まあ、べつに本のままでも話せるならいいんだけど。ただ、作中と違っているので気になる。
『それはお前の力が半端だからだろ。騙されたぜ、天使の気配を感じたと思ったら、それ以上に妙なガキがいたんだからな』
「天使の、気配?」
『なんだ、その間抜けな顔は。お前、天使を知らないのか?』
サルヴァドールは自分から天使について説明してくる。だいたいが前世で得た、私でも把握している知識だったけれど。
それよりも私は、天使の気配という言葉が気になった。
「ねえ、天使の気配ってなに?」
『なにって、そのまんま。お前、血族ではなさそうなのに、匂いがするんだよ、天使の』
サルヴァドールは私の近くに寄って、ふわふわと本を小刻みに揺らす。まるで匂いを嗅がれているみたいだ。
(というか、天使の気配って? 天使要素はリデルの特権なんじゃ??)
まさか私にも秘めたる天使の血筋が、なんて一瞬だけ思ったけど、サルヴァドールの発言はそれとは少し違っている。
『なあ、なんでお前、魂が二つあるんだ』
「へ……魂が、二つ?」
『ああ、一つはかなり特殊だ。つーか、魂が二つあるなんてあり得ねぇ、実はお前化け物か』
失礼な言い草である。
でも、魂が二つと言われて思い当たる節はあった。
二つの魂。一つが今の私なら、もう一つは前世の私のものだ。正直これしか思い当たらないし、たぶん合っているんじゃないかと思うけど。
「魂が二つだと、ダメなの?」
『ダメって話じゃねーけど。天使の匂いがするのは、そっちの特殊なほうからなんだよ。妙に異界の気配もするし』
「ふうん」
前世の私の魂に天使の気配がする。
それってどういうことだろうかと考えてみるが、私の頭で考えつく可能性は限られてくる。
(まさか、この転生も天使のおかげとか? ほら、死ぬときに魂を天国に連れて行ったりする名作劇場アニメとかあったし)
だとしたら、私は天国に連れていくには色々と足りなかったってことなのだろうか。たしかに前世は平凡に生きていて、ものすごく善良な人間だったかというと謎だ。
(え〜、本当にそれでこの世界に飛ばされちゃったってこと? 夢みたいな話だけど、天使の気配ってそれぐらいしか思いつかない)
そもそも、前世触れていたノベルゲームの中に転生してしまうこと自体、夢みたいな話である。それを考えるとなにがあっても不思議じゃない。
『おい、なにか心当たりのある顔だな?』
「う〜ん、あるにはあるかも」
『それ、オレに話せ』
「ええ、でも。アリア、サルヴァドっ……サルのことよくわかんないし」
『人の名を途中で切るな、失礼なガキめ。切る箇所が最悪だぞ』
口にしてみたら案外、発音しづらかったというか。短く切ったらサルになっただけで、悪意はなかったのに。
じゃあサルヴァね、と切る箇所を変えて話を進める。
「サルヴァはわたしの味方になってくれるの? じゃないと、おしえない」
サルヴァドールは私の魂が二つあることに興味をもっている。その些細な興味が、今の私にとっての切り札だ。
どうにかしてサルヴァドールを味方につけたい。そうすればクリストファーのことで助言をもらえるかもしれないし。
『味方って、オレの力を借りたいってことか?』
「うん、そう」
『……それがどういうことかわかって言ってるのか。お前は今、悪魔に力を借りたいって言ってんだぞ』
「そうだね」
『そうだねって、はあ……』
サルヴァドールが言いたいことはよくわかる。
悪魔の力を借りたい、それはすなわち悪魔との契約を視野に入れた言葉だからだ。
そして人間と契約を結ぼうとする悪魔は例外なく、力を貸す見返りに人間の体内に宿る核を喰らおうとする。
例外なくって言ったけど、実はサルヴァドールはその例外だった。
(どうしてかはわからないけど、サルヴァは人間の核に興味がないってゲームで言ってた)
そんなサルヴァドールの目的は、自分以外の悪魔を退けること。だからリデルのそばにいることが彼にとって一番都合がよかったんだけど。
私にはリデルのように悪魔と対抗できるような特殊能力がない。でも、どうにかしてサルヴァドールを仲間に引き入れたい。
「どうしたらサルヴァはわたしの力になってくれる?」
『さっきから力、力って。お前みたいなガキがどんな理由があって力を欲するっていうんだよ』
「……アリアのお父様が、悪魔に狙われてるかもしれないから」
『なに?』
その事実を告げたところ、サルヴァドールの声音が変わる。
『おい、なんでガキがそんなこと知ってるんだ』
「おしえない。力になってくれたらおしえてあげるかも」
『このガキ……』
仕方がないでしょう。私にはこれぐらいしかサルヴァドールの興味を引ける材料がないんだから。そんなイラッとしないで欲しい。
けれど、やっぱり悪魔関連の話題はサルヴァドールにとって重要なことのようだ。
このままうまいこと力になってもらえるようにできないかな。そんなふうに考えていたところで、部屋に誰かが入ってきた。
「……起きていたのか」
扉に目を向けて、私は無意識に口をぽかんと開けてしまった。
こちらを静かに窺うその人は、言いようのない威圧感を漂わせながら私のほうに歩いてくる。
「昨夜、なぜ書庫室にいた?」
前置きもなく放たれた言葉に、私は身を固くした。
寒色の銀の髪と、すべてを見透かそうとするような青の鋭い瞳。意識がはっきりしているときに見るのは初めてだ。
前世の記憶が蘇ってはや1ヶ月。
今まで一度だって部屋を訪れたことがなかったクリストファーが、こんなにもあっさりと部屋にやってきたのだった。