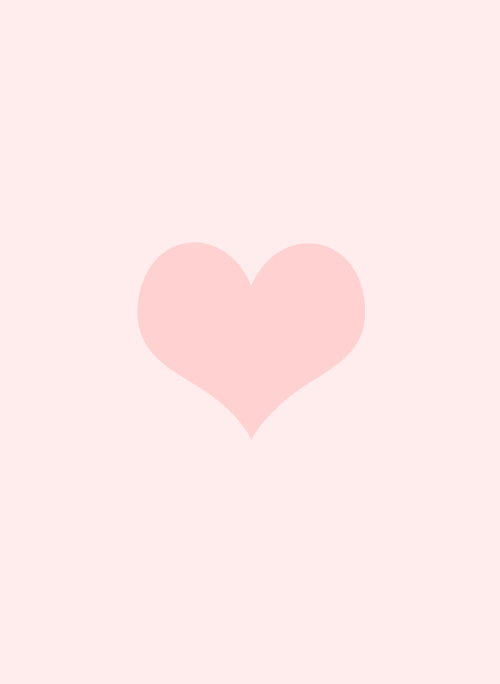目を開けると、見慣れた風景が広がっていた。そこは紛れもなく、実家カブリーニ家の自室だった。
(きっと、テオ様に腹を立てたお父様が、連れ戻してくださったのね)
納得しながらふと姿見を見て、ビアンカはおやと思った。何だか、妙に若く映っているのだ。地味な黒髪とはしばみ色の瞳は変わらないとして、やけに肌がつるつるしている。……そして、髪も垂らしている。まるで、社交界デビュー前のように。
そこへ、ノックの音がした。顔をのぞかせたのは、懐かしい娘だった。
「ジェンマ!」
ビアンカは、思わず声を上げていた。幼い頃から仕えてくれていた侍女で、チェーザリ家へも一緒に付いて来てくれた。だが、テオが彼女に手を出そうとしたのをきっかけに、カブリーニの実家へ帰したのだ。
「久しぶりねえ。元気にしていた?」
するとジェンマは、妙な顔をした。
「お嬢様、何を仰っているのです? 今朝もお会いしたではございませんか」
「今朝?」
「ええ。ところで、ドレスが仕上がりましたよ。どうぞ、ご覧くださいませ」
ビアンカはきょとんとしながら、ジェンマがドレスを広げるのを見ていた。そして、あっと声を上げそうになった。実に思い出深い品だったのだ。デビュタントボール当日に、着ていたドレス。カブリーニ家が貧しいがゆえに、母のドレスを仕立て直したのだが。
「奥様は、謝っておられました。こんな品しか用意してやれなくて、と。でも、ビアンカお嬢様なら大丈夫ですわ! これほど、魅力的でいらっしゃるのですもの。デビューした暁には、男性陣が放っておきませんわ」
励ますように、ジェンマが言う。まさか、とビアンカは思った。
「あの……、ジェンマ。変なことを聞くけれど、今は何年何月かしら?」
ジェンマが、いよいよ首をかしげる。そして彼女が口にした答に、ビアンカは絶叫しそうになった。それはまさしく、ビアンカの社交界デビューの一ヶ月前だったのだ。
(時間が戻ってる……!?)
(きっと、テオ様に腹を立てたお父様が、連れ戻してくださったのね)
納得しながらふと姿見を見て、ビアンカはおやと思った。何だか、妙に若く映っているのだ。地味な黒髪とはしばみ色の瞳は変わらないとして、やけに肌がつるつるしている。……そして、髪も垂らしている。まるで、社交界デビュー前のように。
そこへ、ノックの音がした。顔をのぞかせたのは、懐かしい娘だった。
「ジェンマ!」
ビアンカは、思わず声を上げていた。幼い頃から仕えてくれていた侍女で、チェーザリ家へも一緒に付いて来てくれた。だが、テオが彼女に手を出そうとしたのをきっかけに、カブリーニの実家へ帰したのだ。
「久しぶりねえ。元気にしていた?」
するとジェンマは、妙な顔をした。
「お嬢様、何を仰っているのです? 今朝もお会いしたではございませんか」
「今朝?」
「ええ。ところで、ドレスが仕上がりましたよ。どうぞ、ご覧くださいませ」
ビアンカはきょとんとしながら、ジェンマがドレスを広げるのを見ていた。そして、あっと声を上げそうになった。実に思い出深い品だったのだ。デビュタントボール当日に、着ていたドレス。カブリーニ家が貧しいがゆえに、母のドレスを仕立て直したのだが。
「奥様は、謝っておられました。こんな品しか用意してやれなくて、と。でも、ビアンカお嬢様なら大丈夫ですわ! これほど、魅力的でいらっしゃるのですもの。デビューした暁には、男性陣が放っておきませんわ」
励ますように、ジェンマが言う。まさか、とビアンカは思った。
「あの……、ジェンマ。変なことを聞くけれど、今は何年何月かしら?」
ジェンマが、いよいよ首をかしげる。そして彼女が口にした答に、ビアンカは絶叫しそうになった。それはまさしく、ビアンカの社交界デビューの一ヶ月前だったのだ。
(時間が戻ってる……!?)