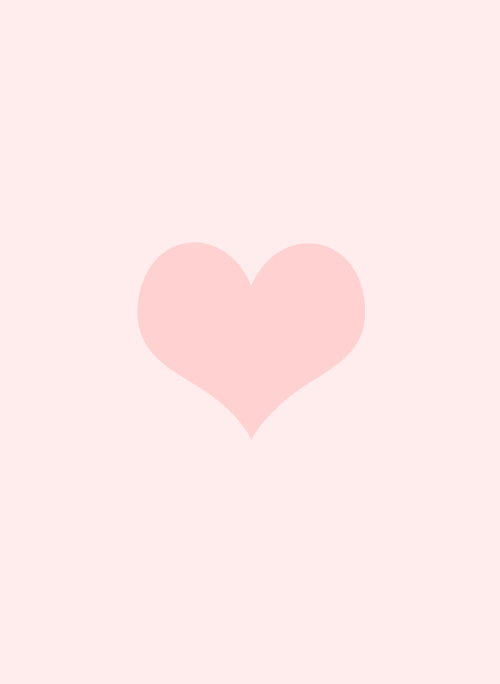一人の食事をさっさと終えると、ビアンカは自ら厨房へ入った。残った料理について、料理番のニコラに、細かく指示をする。
「そうね、これとこれは明日に回しましょう。残ったお肉は、ペーストにするといいわ。パイに入れられるわね」
「かしこまりました、奥様」
ニコラが、神妙に頷く。本来、ここまで奥方が出しゃばるべきでないことはわかっている。だが、そうせねばならないほど、このチェーザリ家の財政は逼迫しているのだ。夫テオが、身の丈に合わない浪費をするせいである。幸いにもビアンカは、料理の心得があった。ビアンカの実家・カブリーニ子爵家は貧しく、使用人は最低限しか雇っていなかったのだ。だからビアンカは、本来貴族の娘がやるべきでない料理をしていたのである。今やビアンカは、日夜ニコラと相談しては、安くて栄養のあるメニューを一緒に考えている。
厨房から出て来ると、ちょうどテオが帰宅した。
「また厨房にいたのか」
テオの体からは、きついアルコールと香水の匂いがする。どうしてこの男の正体を見抜けなかったのだろうと、ビアンカは、彼と出会った頃の自分の愚かさを呪った。テオは、輝くシルバーの髪と、アイスブルーの瞳を持つ美男子だ。婚活疲れしていたということもあり、ビアンカは彼の求婚に飛び付いてしまったのだが、もう少し冷静に考えるべきだった。なぜテオが、家柄も容姿も悪くないにもかかわらず、二十五歳のその年まで独身でいたのかを。
「チェーザリ伯爵夫人ともあろうものが、みっともないとは思わないか」
節約に励まねばならないのは誰のせいだ、と言い返したくなるのを、ビアンカはぐっとこらえた。
「日頃美味しい料理を提供してくれる、ニコラを慰労していたのでございます……。今夜も、素晴らしいスープを作ってくれたのですよ? ……ああ、まだ残っておりますわ」
持って来るよう、執事に合図する。本当のことだ。少ない食費をやりくりして購入した、野菜と肉入りスープである。味はもちろん、栄養バランスも抜群だ。だがテオは、眉間の皺を深くした。
「ふん。来る日も来る日も、厨房に入り浸って……。まさか、ニコラとできておるのではあるまいな」
「な……、何ですって!?」
あまりの言葉に、ビアンカは愕然とした。
「そうね、これとこれは明日に回しましょう。残ったお肉は、ペーストにするといいわ。パイに入れられるわね」
「かしこまりました、奥様」
ニコラが、神妙に頷く。本来、ここまで奥方が出しゃばるべきでないことはわかっている。だが、そうせねばならないほど、このチェーザリ家の財政は逼迫しているのだ。夫テオが、身の丈に合わない浪費をするせいである。幸いにもビアンカは、料理の心得があった。ビアンカの実家・カブリーニ子爵家は貧しく、使用人は最低限しか雇っていなかったのだ。だからビアンカは、本来貴族の娘がやるべきでない料理をしていたのである。今やビアンカは、日夜ニコラと相談しては、安くて栄養のあるメニューを一緒に考えている。
厨房から出て来ると、ちょうどテオが帰宅した。
「また厨房にいたのか」
テオの体からは、きついアルコールと香水の匂いがする。どうしてこの男の正体を見抜けなかったのだろうと、ビアンカは、彼と出会った頃の自分の愚かさを呪った。テオは、輝くシルバーの髪と、アイスブルーの瞳を持つ美男子だ。婚活疲れしていたということもあり、ビアンカは彼の求婚に飛び付いてしまったのだが、もう少し冷静に考えるべきだった。なぜテオが、家柄も容姿も悪くないにもかかわらず、二十五歳のその年まで独身でいたのかを。
「チェーザリ伯爵夫人ともあろうものが、みっともないとは思わないか」
節約に励まねばならないのは誰のせいだ、と言い返したくなるのを、ビアンカはぐっとこらえた。
「日頃美味しい料理を提供してくれる、ニコラを慰労していたのでございます……。今夜も、素晴らしいスープを作ってくれたのですよ? ……ああ、まだ残っておりますわ」
持って来るよう、執事に合図する。本当のことだ。少ない食費をやりくりして購入した、野菜と肉入りスープである。味はもちろん、栄養バランスも抜群だ。だがテオは、眉間の皺を深くした。
「ふん。来る日も来る日も、厨房に入り浸って……。まさか、ニコラとできておるのではあるまいな」
「な……、何ですって!?」
あまりの言葉に、ビアンカは愕然とした。