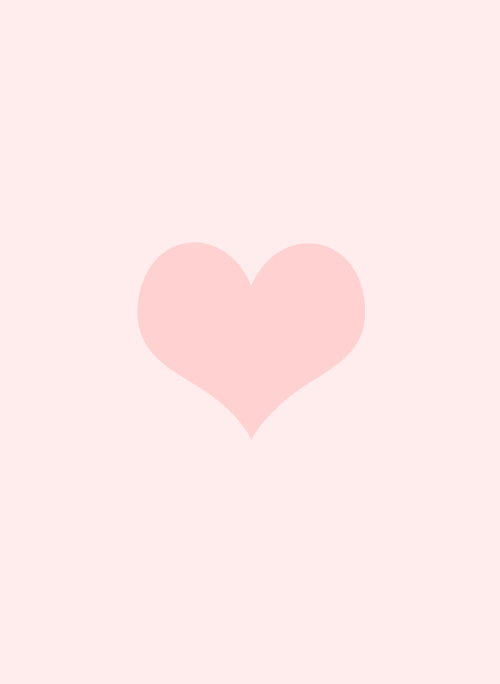「ビアンカ嬢、返事は?」
ステファノが、優しく促す。ビアンカは、喉がカラカラに渇くのを感じていた。
(信じられない。夢みたいに、幸せだわ)
ずっと想ってきた男性なのだから。嬉しくないはずがなかった。『好きな男から求婚されたら、意地は張らない方がいい』というアントニオの言葉も、脳裏には蘇っていた。
「案ずることはないぞ? そなたならやっていけると、私も信じている」
横から口を挟んだのは、ゴドフレードだった。イレーネも隣で頷いているところをみると、王太子夫妻も、事前に承知していたのだろう。
夫妻の温かい眼差しに、ビアンカは思わず、首を縦に振りそうになった。肯定の返事が、喉元まで出かかる。だがその瞬間、イレーネの膨らんだ腹が目に飛び込んだ。
(お子! 私は、子を成せるだろうか……)
テオと結婚していた一年半の間、ビアンカは身ごもることがなかったのだ。当時は、そのうち授かるだろうと楽観視していたが、王弟妃ともなればそんな悠長なことは言っていられない。いくら第二王子とはいえ、跡継ぎがもうけられないとなったら、一大事だ。
(それに。何よりステファノ殿下ご自身が、お子を望まれているわ……)
つい先ほども、ゴドフレード夫妻にそう言っていたではないか。ビアンカは、口にしかけた言葉を、かろうじて飲み込んだ。代わりに、反対の言葉を告げる。
「大変、恐れ多いお話なれど……。お受けすることはいたしかねます」
周囲からは、一斉に非難の声が上がった。
「何様のつもりかしら?」
「いい気になって……」
ステファノは、彼らを制すると、やや首をかしげた。
「騎士団寮の仕事なら、心配はない。そなたの代役は用意するし、王宮へ入った後も、自由に料理をしてよいのだぞ?」
「ご厚意はありがたいのですが、そういう問題ではありません」
まさか、人生をやり直しましたなどと言えるわけがない。ビアンカは、泣きそうになるのをこらえて、必死に言葉をつむいだ。
「数々のご配慮、もったいないお言葉、本当にありがとうございました。身に余る光栄と、深く感謝しております。ですが、私のことは、もうお忘れくださいませ。私は今後も、一料理番として生きていく所存です」
ビアンカは、ドレスの裾を翻して駆け出した。勢いに呑まれたのか、周囲が道を空ける。そのまま会場を出たが、さすがにステファノも引き留めることはしなかった。
ステファノが、優しく促す。ビアンカは、喉がカラカラに渇くのを感じていた。
(信じられない。夢みたいに、幸せだわ)
ずっと想ってきた男性なのだから。嬉しくないはずがなかった。『好きな男から求婚されたら、意地は張らない方がいい』というアントニオの言葉も、脳裏には蘇っていた。
「案ずることはないぞ? そなたならやっていけると、私も信じている」
横から口を挟んだのは、ゴドフレードだった。イレーネも隣で頷いているところをみると、王太子夫妻も、事前に承知していたのだろう。
夫妻の温かい眼差しに、ビアンカは思わず、首を縦に振りそうになった。肯定の返事が、喉元まで出かかる。だがその瞬間、イレーネの膨らんだ腹が目に飛び込んだ。
(お子! 私は、子を成せるだろうか……)
テオと結婚していた一年半の間、ビアンカは身ごもることがなかったのだ。当時は、そのうち授かるだろうと楽観視していたが、王弟妃ともなればそんな悠長なことは言っていられない。いくら第二王子とはいえ、跡継ぎがもうけられないとなったら、一大事だ。
(それに。何よりステファノ殿下ご自身が、お子を望まれているわ……)
つい先ほども、ゴドフレード夫妻にそう言っていたではないか。ビアンカは、口にしかけた言葉を、かろうじて飲み込んだ。代わりに、反対の言葉を告げる。
「大変、恐れ多いお話なれど……。お受けすることはいたしかねます」
周囲からは、一斉に非難の声が上がった。
「何様のつもりかしら?」
「いい気になって……」
ステファノは、彼らを制すると、やや首をかしげた。
「騎士団寮の仕事なら、心配はない。そなたの代役は用意するし、王宮へ入った後も、自由に料理をしてよいのだぞ?」
「ご厚意はありがたいのですが、そういう問題ではありません」
まさか、人生をやり直しましたなどと言えるわけがない。ビアンカは、泣きそうになるのをこらえて、必死に言葉をつむいだ。
「数々のご配慮、もったいないお言葉、本当にありがとうございました。身に余る光栄と、深く感謝しております。ですが、私のことは、もうお忘れくださいませ。私は今後も、一料理番として生きていく所存です」
ビアンカは、ドレスの裾を翻して駆け出した。勢いに呑まれたのか、周囲が道を空ける。そのまま会場を出たが、さすがにステファノも引き留めることはしなかった。