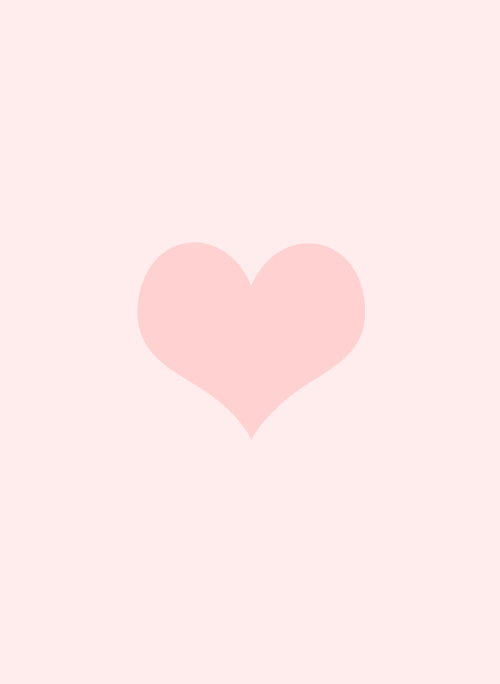社交界デビュー前、一応ダンスは習った。この新しい人生では、つい最近まで練習していたことになるから、両親は心配しなかったのだろう。とはいえ実際のビアンカは、最近までチェーザリ夫人だったわけである。テオと結婚していた期間は、屋敷の管理に追われており、舞踏会どころではなかった。ステップは、すっかり忘れている。
「全く、経験がないと申すか?」
ステファノは、動じるでもなかった。いえ、とビアンカは小さく答えた。
「以前、習いました。ですが、経験が乏しく……」
社交界デビューはせず、料理番をしてきたことになっているから、つじつまは合う。ステファノは、納得したように頷いた。
「ふむ。では、基本は、知っておるのだな?」
はいと答えると、ステファノは満足そうに微笑んだ。
「ならば、問題はない。この一週間で、特訓いたせ。私が教えよう」
「一週間で、特訓ですか……。承知しま……、じゃなくて、ええ!? 殿下がですか?」
ビアンカは仰天した。最後に、とんでもないフレーズが付け加わらなかったか。
「めめめ、滅相もない!」
「私のコーチでは、不安と申すか? 運動神経は悪くないと、自負しておるが」
何を勘違いしたのか、ステファノはムッとしたような顔をした。確かにステファノといえば、武芸一筋で、舞踏会でダンスを披露している姿はあまり見たことがない。だが、問題はそこではなかった。
「いえ、そうではなく……。恐れ多いと、申しているのです」
「だが、他に教えてくれそうな知り合いが、この王宮内におるのか?」
ビアンカは、うっとつまった。
「妹が、今こちらへ来ております。彼女は、ダンスが得意です」
「だが妹君では、男性パートは務まらないのではないか?」
「……」
黙り込むビアンカを見て、ステファノは愉快そうに笑った。
「決まりだな。この一週間、そなたのために時間を空けるから、練習いたそう。よかったではないか。ダラダラ過ごすのは、嫌なのであろう?」
ビアンカは、がくりと頭を垂れた。
(何だか、完全に丸め込まれた気がするわ……)
「全く、経験がないと申すか?」
ステファノは、動じるでもなかった。いえ、とビアンカは小さく答えた。
「以前、習いました。ですが、経験が乏しく……」
社交界デビューはせず、料理番をしてきたことになっているから、つじつまは合う。ステファノは、納得したように頷いた。
「ふむ。では、基本は、知っておるのだな?」
はいと答えると、ステファノは満足そうに微笑んだ。
「ならば、問題はない。この一週間で、特訓いたせ。私が教えよう」
「一週間で、特訓ですか……。承知しま……、じゃなくて、ええ!? 殿下がですか?」
ビアンカは仰天した。最後に、とんでもないフレーズが付け加わらなかったか。
「めめめ、滅相もない!」
「私のコーチでは、不安と申すか? 運動神経は悪くないと、自負しておるが」
何を勘違いしたのか、ステファノはムッとしたような顔をした。確かにステファノといえば、武芸一筋で、舞踏会でダンスを披露している姿はあまり見たことがない。だが、問題はそこではなかった。
「いえ、そうではなく……。恐れ多いと、申しているのです」
「だが、他に教えてくれそうな知り合いが、この王宮内におるのか?」
ビアンカは、うっとつまった。
「妹が、今こちらへ来ております。彼女は、ダンスが得意です」
「だが妹君では、男性パートは務まらないのではないか?」
「……」
黙り込むビアンカを見て、ステファノは愉快そうに笑った。
「決まりだな。この一週間、そなたのために時間を空けるから、練習いたそう。よかったではないか。ダラダラ過ごすのは、嫌なのであろう?」
ビアンカは、がくりと頭を垂れた。
(何だか、完全に丸め込まれた気がするわ……)