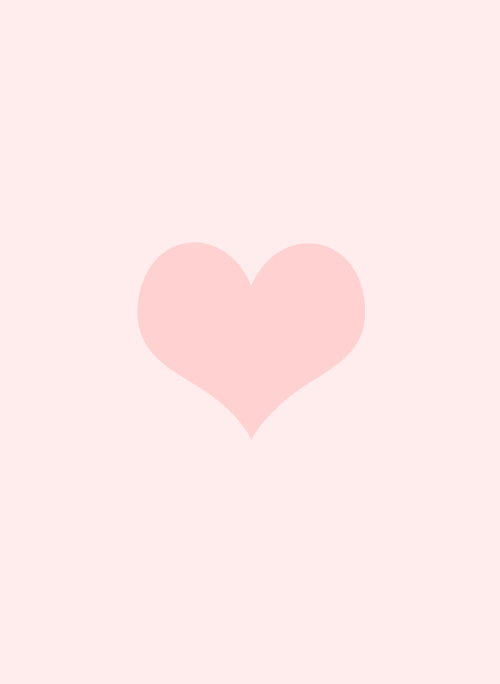「ダメダメ。まだあんた一人にゃ、任せられないよ」
厳しく告げられて、スザンナはしゅんと落ち込んだ。でも、とエルマが微笑む。
「手伝ってくれるのは、大歓迎さ。近々この寮も、メンバーが増えるらしいからね。人手が増えるのは、ありがたい」
ボネッリ伯爵は、例のアントニオのビフォア・アフター絵を、宣伝に用いたのである。おかげで騎士団への入団希望者は、どっと増えた。料理が美味いらしい、という噂も、それに拍車をかけたらしかった。
「姉妹ともども、お世話になります。エルマさん、引き続き、色々教えてくださいね」
ビアンカは、力強く訴えた。エルマが、苦笑気味に頷く。
「そりゃそうさ。王子殿下のスカウトをお断りしてまで、ここへ残ってくれたんだからね。責任を持って、指導しないと」
早寝の習慣があるエルマは、ビアンカがステファノの要請を突っぱねたあの騒ぎを、寝ていて知らなかったのだ。翌朝その事実を知った彼女は、青ざめていた。
「しかし、あたしも人のことは言えないけれど、あんたは頑固な子だよ。下手をすれば、不敬の罪に問われていたかもしれないのに、どうしてそう、強情を張るんだか」
「この人生では、料理番の道を極めると、心に決めましたから」
ビアンカは、胸を張った。ステファノやボネッリ伯爵に告げたことは、本音だ。自分は、王子の食事を担当できるようなレベルではない。自分で自分に納得がいくまで、料理の腕を磨きたかった。
(……それに)
ビアンカは、怖かったのだ。ステファノがここにいる間、プレゼントをもらったり、食事に同席させられたりと、思いがけぬ厚遇を受けた。これ以上彼と関われば、欲が湧いてしまいそうだったのだ。男性には目を向けない、仕事に生きると、誓ったというのに。その誓いを破ってしまいそうな気がした。
(でも、もう大丈夫ね……)
ステファノは、もう王都へ帰った。しかもその後、パルテナンド王国を離れたのだ。他国から攻め込まれた同盟国ロジニアが、援軍を要請したため、加勢に駆け付けたのである。今頃は戦場で、雄々しく戦っていることと思われた。ドナーティ、アントニオも付き従ったとのことである。
「この人生?」
エルマが、きょとんとする。ビアンカは、慌てた。
「いえ、深い意味はありません。ところで、不敬罪だなんて、大げさですわ」
「大げさなものかね。あんたはまだ、世間知らずの小娘だから……」
その時、玄関の方で、何やら騒がしい気配がした。急いで外へ出て、ビアンカたちは唖然とした。
何台ものいかめしい馬車が、騎士団寮の前に整列していたのだ。王立騎士団の制服を着た、リーダーらしき男が降りて来る。そして、ビアンカに向かって告げた。
「ビアンカ・ディ・カブリーニ。パルテナンド王室反逆の罪で、逮捕する」
えーっと、ビアンカは叫びそうになった。
(まさか、本当に……!?)
厳しく告げられて、スザンナはしゅんと落ち込んだ。でも、とエルマが微笑む。
「手伝ってくれるのは、大歓迎さ。近々この寮も、メンバーが増えるらしいからね。人手が増えるのは、ありがたい」
ボネッリ伯爵は、例のアントニオのビフォア・アフター絵を、宣伝に用いたのである。おかげで騎士団への入団希望者は、どっと増えた。料理が美味いらしい、という噂も、それに拍車をかけたらしかった。
「姉妹ともども、お世話になります。エルマさん、引き続き、色々教えてくださいね」
ビアンカは、力強く訴えた。エルマが、苦笑気味に頷く。
「そりゃそうさ。王子殿下のスカウトをお断りしてまで、ここへ残ってくれたんだからね。責任を持って、指導しないと」
早寝の習慣があるエルマは、ビアンカがステファノの要請を突っぱねたあの騒ぎを、寝ていて知らなかったのだ。翌朝その事実を知った彼女は、青ざめていた。
「しかし、あたしも人のことは言えないけれど、あんたは頑固な子だよ。下手をすれば、不敬の罪に問われていたかもしれないのに、どうしてそう、強情を張るんだか」
「この人生では、料理番の道を極めると、心に決めましたから」
ビアンカは、胸を張った。ステファノやボネッリ伯爵に告げたことは、本音だ。自分は、王子の食事を担当できるようなレベルではない。自分で自分に納得がいくまで、料理の腕を磨きたかった。
(……それに)
ビアンカは、怖かったのだ。ステファノがここにいる間、プレゼントをもらったり、食事に同席させられたりと、思いがけぬ厚遇を受けた。これ以上彼と関われば、欲が湧いてしまいそうだったのだ。男性には目を向けない、仕事に生きると、誓ったというのに。その誓いを破ってしまいそうな気がした。
(でも、もう大丈夫ね……)
ステファノは、もう王都へ帰った。しかもその後、パルテナンド王国を離れたのだ。他国から攻め込まれた同盟国ロジニアが、援軍を要請したため、加勢に駆け付けたのである。今頃は戦場で、雄々しく戦っていることと思われた。ドナーティ、アントニオも付き従ったとのことである。
「この人生?」
エルマが、きょとんとする。ビアンカは、慌てた。
「いえ、深い意味はありません。ところで、不敬罪だなんて、大げさですわ」
「大げさなものかね。あんたはまだ、世間知らずの小娘だから……」
その時、玄関の方で、何やら騒がしい気配がした。急いで外へ出て、ビアンカたちは唖然とした。
何台ものいかめしい馬車が、騎士団寮の前に整列していたのだ。王立騎士団の制服を着た、リーダーらしき男が降りて来る。そして、ビアンカに向かって告げた。
「ビアンカ・ディ・カブリーニ。パルテナンド王室反逆の罪で、逮捕する」
えーっと、ビアンカは叫びそうになった。
(まさか、本当に……!?)