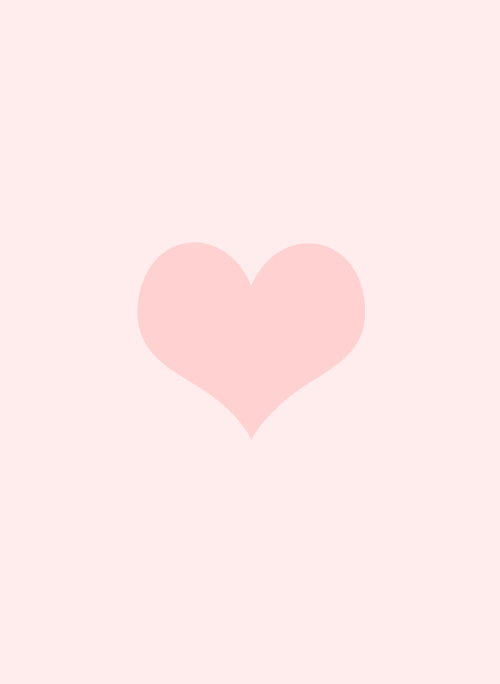「悪いことは言わないから、さっさとお家へお帰り。貴族のお嬢様に、食材の買い出しなんてできるものかね。どうせ、スプーンより重い物は持ったことがないクチだろう?」
「お言葉ですが」
ビアンカは、エルマをキッと見返した。
「貴族といえども、うちは貧乏子爵です。使用人がやるようなことも、率先してやって来ました。買い出しくらい、やってみせます!」
思いきり我が家の恥をさらしている気もするが、まずはエルマに認めてもらわないことには始まらない。だがエルマの表情は、ますます険しくなった。
「やれやれ。そこまで男日照りなのかい」
「――はい!?」
思いがけない言葉に、ビアンカは仰天した。エルマが、不機嫌そうにため息を吐く。
「これで何人目だろうねえ。うちの男連中目当てで、働きたがる娘。連中の気を引くことしか考えてないから、ロクに役立たなかったもんだ。あんたも、同類だろう? 貴族のお嬢様とはいっても、その貧相な容姿じゃ、男はつかまりそうにないものな」
ビアンカは、カッとなった。貧相な容姿は真実だが、そんな風に思われていたなんて、心外だ。
「私……、そんなんじゃありません! 私は結婚せずに、仕事に生きる人生を送りたいんです。だからこちらで、料理番として働かせていただきたいんです!」
それでも、エルマの眼差しは冷ややかだった。
「どうだかね。まあいずれにしても、あんたは買い出しだけやっとくれ。ここの料理は、あたしの仕事だ。首をつっこむんじゃないよ」
「そんなあ……」
絶望するビアンカに、エルマはメモを押し付けた。
「というわけで、早速仕事だ。今すぐ買い物に行っとくれ」
「今ですか?」
まだ、部屋も案内してもらっていなければ、荷物も置いていないというのに。エルマが、目をつり上げる。
「早く行かないと、夕飯に間に合わないだろうが。それとも、仕事に生きるってのは嘘かい?」
「……行かせていただきます」
ビアンカは、渋々メモを受け取った。やはり男性目当てだったのか、と思われるのは癪だからだ。
(まずは、買い出しの仕事をきっちりやり遂げよう。地道に頑張っていれば、エルマさんもきっと認めてくれるはず……)
「お言葉ですが」
ビアンカは、エルマをキッと見返した。
「貴族といえども、うちは貧乏子爵です。使用人がやるようなことも、率先してやって来ました。買い出しくらい、やってみせます!」
思いきり我が家の恥をさらしている気もするが、まずはエルマに認めてもらわないことには始まらない。だがエルマの表情は、ますます険しくなった。
「やれやれ。そこまで男日照りなのかい」
「――はい!?」
思いがけない言葉に、ビアンカは仰天した。エルマが、不機嫌そうにため息を吐く。
「これで何人目だろうねえ。うちの男連中目当てで、働きたがる娘。連中の気を引くことしか考えてないから、ロクに役立たなかったもんだ。あんたも、同類だろう? 貴族のお嬢様とはいっても、その貧相な容姿じゃ、男はつかまりそうにないものな」
ビアンカは、カッとなった。貧相な容姿は真実だが、そんな風に思われていたなんて、心外だ。
「私……、そんなんじゃありません! 私は結婚せずに、仕事に生きる人生を送りたいんです。だからこちらで、料理番として働かせていただきたいんです!」
それでも、エルマの眼差しは冷ややかだった。
「どうだかね。まあいずれにしても、あんたは買い出しだけやっとくれ。ここの料理は、あたしの仕事だ。首をつっこむんじゃないよ」
「そんなあ……」
絶望するビアンカに、エルマはメモを押し付けた。
「というわけで、早速仕事だ。今すぐ買い物に行っとくれ」
「今ですか?」
まだ、部屋も案内してもらっていなければ、荷物も置いていないというのに。エルマが、目をつり上げる。
「早く行かないと、夕飯に間に合わないだろうが。それとも、仕事に生きるってのは嘘かい?」
「……行かせていただきます」
ビアンカは、渋々メモを受け取った。やはり男性目当てだったのか、と思われるのは癪だからだ。
(まずは、買い出しの仕事をきっちりやり遂げよう。地道に頑張っていれば、エルマさんもきっと認めてくれるはず……)