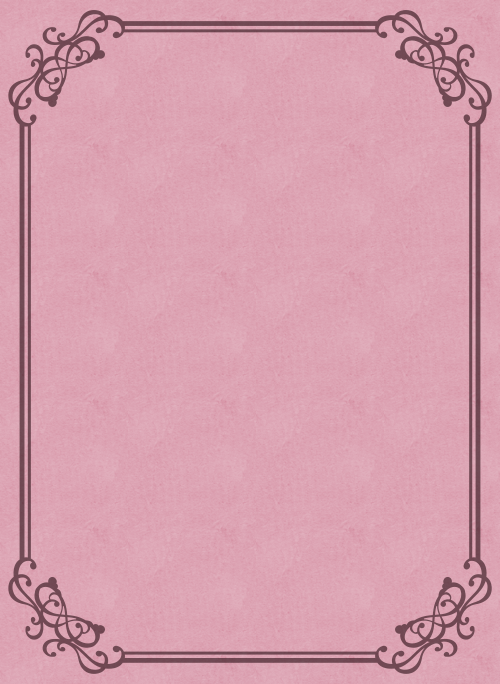その地に降り立ったのは、現地時間で午後8時を回ったところだった。
風は生暖かく、ここが赤道直下の地であることを嫌でも思い出させた。
「いや〜、やっと着いたな!よっ!シンガポーーーーールッ!」
日も出てないのにサングラスを掛けて、Tシャツ短パン姿の中年男性に、私を含めた他の4人の反応は様々だ。
「朝比奈教授、ずっと楽しみにしてましたもんねっ」
キャピッと明るい茶髪を跳ねさせて、入局一年目の篠塚明里はわかりやすくテンションが上がっている。
「教授、とりあえず飯行きましょうよ。腹減って死にそうっす」
飛行機の座席の幅もギリギリだったガタイの良い男は講師の志摩先生だ。こちらもわかりやすく腹に手を当てて、空腹をアピールしている。
「いや、先にホテルに荷物を置きましょう。とりあえず俺が先導するからーー、吉野、お前あの危なかっしい二人をちゃんと見てろよ」
そう、この熱気に当てられもせず冷静に私に指示を出すのは、同期の真田恭太である。
「危なかっしい二人って、教授と明里ちゃん?」
「他に誰がいるーー」
「なんか俺おしっこ行きたくなっちゃったなー。恭太、先行っててくれ〜」
「え、ちょっと志摩先生どこ行くんですか!あぁ、くそ!危なっかしいのは三人の間違いだ、吉野、お前ホテルの場所分かるか?先に教授たちと行っててくれ、俺は志摩先生についてくから!」
「はは、分かった分かった。今回も大変そうだよね、お互い」
「まじで吉野しか頼れる人間がいないわ…」
ため息を吐きながら、真田がキャリーケースを引き摺って、そのまま志摩に着いていく後ろ姿を見送った。
教授と明里を見ると、既に二人で写真を撮りあってはしゃいでいる。なんとまぁ、呑気なものだ。
また生温い風が吹いて、私は降り立ったばかりの異国の空を見上げる。眩い地球の灯りのせいで星はまばらにしか見えなかったけれど、それでも日本と違う空に心は自然浮き立つ。
久々の海外での皮膚科学会だった。本当は私だって、教授や明里に負けず劣らずワクワクしている。明里が私を振り返り、顔いっぱいの笑顔で手を振ってくる。
「果穂先生っ!一緒に写真撮りましょうよ!」
「吉野、お前が写真撮れ!篠塚先生、手ブレ酷くて全然駄目なんだよ。これじゃあ子供たちに写真送れなくて困る」
「そんな、教授ひどい!下っ端にも優しくして欲しい」
「皮膚科医が写真撮るの下手でどうするんだよ」
「あはは」
教授と明里の掛け合いに笑いながら、私は二人の元に向かった。