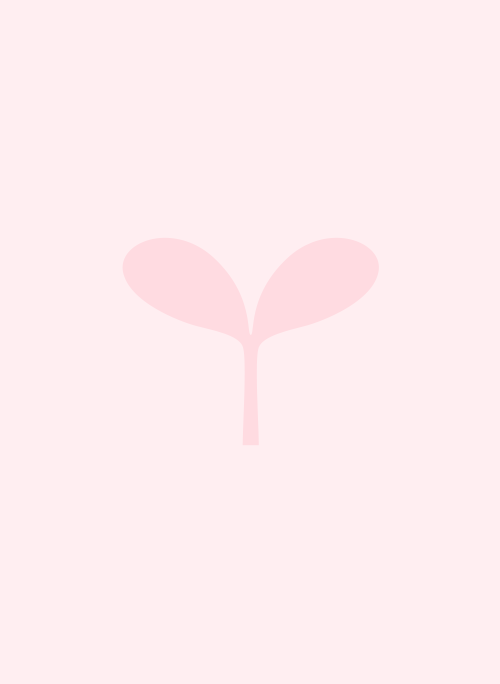その日から空が晴れることはなかった。小雨だったり大雨だったり、くもっていたり。
「なぁにがミハルだぁ…!アツはまた、面倒な娘を引き取ったな!」
「あの子が外にいりゃずっと雨だ…。」
「晴れなきゃ作物も育ちゃしないよ!」
隣の村から親戚を頼って来た娘のことだ。
その娘が外に出た日は、決して晴れないと言われていた。
「ミハル…悪いげっとな……?」
「おいちゃん、分かってる…あたいは外に出るな、って…」
「悪りぃなぁ…」
十にもならない好奇心な年頃の娘に、優しい叔父はいつものようにそう言って頭を下げる。
「おいちゃんなんも悪くない。あたいが外に出っと雨降っから…」
「ミハルのせいで無ぇよ…!…行ってくっから…」
「うん…」
ミハルは仕事に出掛ける叔父の言いつけを守り、決して外へは出ずに家の中で遊び、出来る家の手伝いをする。外に出れば村の他の人間が、あの娘が外へ出ると必ず雨が降る、と言い、ミハルと叔父の二人を責めるのだから。
「あたいのせいなんだ……」
前の村にいた頃はそんなことはなかった。
両親が亡くなって、叔父に引き取られてこの村に来て、初めて言われたことだ。
外に出る、たったそれだけのことが許されないミハルは、いつも昼は一人ぼっちだった。もちろん友達と呼べる相手など、近くにいるはずも無い。
ある日の夜だった。
小さな小さな音で、笛太鼓の音と歌が聞こえた。
「あめをつれてここにくる〜♪あめかみさまがやってくる〜♪」
「なんだべ?」
起きたのはミハル一人。叔父は仕事に疲れて寝ているようだった。
外はだいぶ珍しく晴れ、月も星も見える。ミハルが戸の隙間からそっとのぞくと、見えたのは子ぎつね二匹と子だぬき一匹。三匹とも、二足でひょっこり立って、色鮮やかなヒラヒラした着物を羽織り、小さな小さな声で歌い、小さな小さな笛を吹き、小さな腹の太鼓を叩いて踊っていた。
「…!」
あまりに楽しげだったので、ミハルは外に出てその様子をすぐそばで見たいと思ったが、
「……あたい、外は出ちゃいけないんだ…」
思い返して小さくつぶやき、飛び出していきたい気持ちをこらえ、そのまま様子を見ていた。
「なぁにがミハルだぁ…!アツはまた、面倒な娘を引き取ったな!」
「あの子が外にいりゃずっと雨だ…。」
「晴れなきゃ作物も育ちゃしないよ!」
隣の村から親戚を頼って来た娘のことだ。
その娘が外に出た日は、決して晴れないと言われていた。
「ミハル…悪いげっとな……?」
「おいちゃん、分かってる…あたいは外に出るな、って…」
「悪りぃなぁ…」
十にもならない好奇心な年頃の娘に、優しい叔父はいつものようにそう言って頭を下げる。
「おいちゃんなんも悪くない。あたいが外に出っと雨降っから…」
「ミハルのせいで無ぇよ…!…行ってくっから…」
「うん…」
ミハルは仕事に出掛ける叔父の言いつけを守り、決して外へは出ずに家の中で遊び、出来る家の手伝いをする。外に出れば村の他の人間が、あの娘が外へ出ると必ず雨が降る、と言い、ミハルと叔父の二人を責めるのだから。
「あたいのせいなんだ……」
前の村にいた頃はそんなことはなかった。
両親が亡くなって、叔父に引き取られてこの村に来て、初めて言われたことだ。
外に出る、たったそれだけのことが許されないミハルは、いつも昼は一人ぼっちだった。もちろん友達と呼べる相手など、近くにいるはずも無い。
ある日の夜だった。
小さな小さな音で、笛太鼓の音と歌が聞こえた。
「あめをつれてここにくる〜♪あめかみさまがやってくる〜♪」
「なんだべ?」
起きたのはミハル一人。叔父は仕事に疲れて寝ているようだった。
外はだいぶ珍しく晴れ、月も星も見える。ミハルが戸の隙間からそっとのぞくと、見えたのは子ぎつね二匹と子だぬき一匹。三匹とも、二足でひょっこり立って、色鮮やかなヒラヒラした着物を羽織り、小さな小さな声で歌い、小さな小さな笛を吹き、小さな腹の太鼓を叩いて踊っていた。
「…!」
あまりに楽しげだったので、ミハルは外に出てその様子をすぐそばで見たいと思ったが、
「……あたい、外は出ちゃいけないんだ…」
思い返して小さくつぶやき、飛び出していきたい気持ちをこらえ、そのまま様子を見ていた。